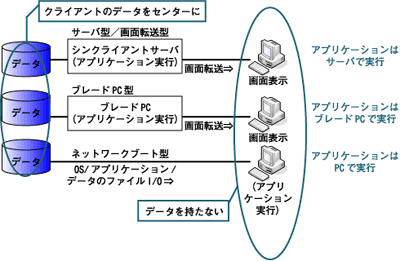| ||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| シンクライアントに対する期待と現状 | ||||||||||
PC(パソコン)からの情報漏洩が社会問題として様々なメディアで取り上げられる昨今、セキュリティの観点からシンクライアントが再び注目を集めている。本連載では、当社が開発した新しいタイプのシンクライアントシステムである「FlexClient」を紹介していく。 一般的にシンクライアントとは、ローカルディスクなどの記憶装置を持たないPCや端末のことを示すことが多い。またこのようなシンクライアント端末は、必ずサーバやストレージなど、センターにあるシステムと組み合わせて使用する。 そこで本連載では、ローカルディスクなどの記憶装置を持たないPCや端末のことを「シンクライアント端末」、またセンターにあるシステムまでを含めたものを「シンクライアントシステム」と呼ぶ。 さて、シンクライアントシステムには様々な方式が存在する。本連載では、まず表1にあげる3種類に分類して、説明していく(図1)。
表1:本連載で取り上げるシンクライアント | ||||||||||
| サーバ型/画面転送型 | ||||||||||
1つ目の「サーバ型/画面転送型」は、「シンクライアント」というキーワードから最初に思い浮かべる仕組みだろう。普段PCで動かしているアプリケーションをサーバ上で動かし、シンクライアント端末にはその画面情報だけが送られてくる。そのためサーバ型または画面転送型と呼ばれている。最近では、仮想OS技術を使って、サーバ内でクライアントOSを複数動かすものもある。 いずれにせよ、PCで動かすアプリケーションをサーバで動かすので、利用者の数に応じた処理能力を持つサーバを用意する必要がある。 | ||||||||||
| ブレードPC型 | ||||||||||
2つ目の「ブレードPC型」は、PCの本体(ブレードPC)だけをセンターに集め、ディスプレイとキーボードのみを延長コードでオフィスまで引いてきた姿をイメージいただきたい。最近は、「サーバ型/画面転送型」と同じく、ネットワーク経由で画面転送を受けるためのシンクライアント端末を利用するものが主流になってきた。 | ||||||||||
| ネットワークブート型 | ||||||||||
3つ目の「ネットワークブート型」は、PCに内蔵されているローカルディスク装置のケーブルを延長し、センターに集めた姿を想像していただけるとわかりやすい。通常はPCのローカルディスク装置のかわりとして、ネットワークに接続されたストレージを用いる。PCは、OSブートからファイルのアクセスまで、このストレージ上の論理ディスクを利用するため、ネットワークブート型と呼ばれる。 「サーバ型/画面転送型」や「ブレードPC型」と大きく異なる点は、アプリケーションがセンターに設置されたサーバやブレードPCではなく、クライアントPCで実行されることである。 | ||||||||||
| それぞれの違い | ||||||||||
以上のように、シンクライアントシステムといわれる仕組みは、いずれの方式もセンターにクライアントが持っていたデータ、方法によってはCPU・メモリなどのリソースを集め、クライアントにはデータを持たせず、常時ネットワークで接続する構成であるといえる。 | ||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||