 |
|
|
| 1 2 3 次のページ
|
 |
| スナップショット機能とは?
|
スナップショットとはある瞬間のファイルシステムのイメージを保持したものです。イメージ作成後は元のボリュームに対して、通常通りファイルの更新や参照を許可しますが、スナップショットを取っておくことで特定の時点のデータにアクセスすることが可能となります。
スナップショットを取るデータが大きい場合でも、ポインタ情報を取得するだけですので、イメージの作成は数秒程度で完了します。その詳細な仕組みはハードウェアやソフトウェアの種類によって若干異なる場合もありますが、大まかな原理は同じです。
実際どのような動きになっているのかを、Linux上でLVMを使用してスナップショットを作成する例を取って見てみます。まずは図1を見てください。
|
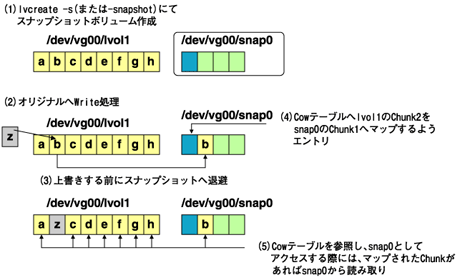
図1:スナップショットの図解
(画像をクリックすると別ウィンドウに拡大図を表示します)
|
まず"lvcreate -s"コマンドでスナップショットを作成します。その後、元のボリュームに対して更新処理をおこなおうとした場合、チャンクサイズ単位で更新対象のデータをスナップショットボリュームへ退避します。
スナップショットボリュームは読み取り専用でアクセスでき、変更が無いブロックにアクセスされた場合は、変更記録が保存されているCow(Copy on Write)テーブルを参照し、ポインタ情報を利用してオリジナルのブロックへアクセスします。元データに変更があったブロックにアクセスする場合は、退避されたスナップショットボリュームから読み出します。
変更箇所のみを保持することで、全てのデータをミラーのようにコピーする場合よりも、格段に少ない容量で特定の静止点のデータにアクセスすることができるのです。
スナップショットの活用方法は色々と考えられますが、単にディスク上のポインタ情報であるため、同一ストレージ上で最終的なバックアップ用途として利用することはできません。定期的に作成することで、ユーザなどのオペレーションミスの際にバックアップ媒体からの復旧を必要としないリカバリに使用されたり、データベースのバックアップの効率化に使用されることが多いようです。
|
| ハードウェアベースのスナップショット
|
こうした便利なスナップショット機能は、現在の大手ストレージベンダーが提供する大規模向けRAID装置ではほとんどが搭載されていますが、各社で機能に関する名称が異なっています。FC/SCSI接続のRAID装置だけでなく、NASの場合にも高機能な製品では搭載されており、その代表格はNetApp社のFiler製品であるといえます。
製品ごとにその管理方法は異なっていますが、多くの場合はホスト側から特定の時点で自由にスナップショットの作成が可能になるように専用のユーティリティが導入されています。ハードウェアとソフトウェアが一括して導入されるため、導入しやすくサポートも受けやすいという利点がありますが、トータルコストが高くなる傾向があります。表1はストレージベンダーが提供しているスナップショットの製品一覧です。
|
|
|
表1:ストレージベンダーのスナップショット製品
|
1 2 3 次のページ
|

|

|

|
著者プロフィール
バックボーン・ソフトウエア株式会社 青木 浩朗
ストレージ専業ベンダーにて、SEおよび企画を担当した後に、2001年にBakBoneSoftware入社。主に大手ベンダーのSEを担当しながら、テクニカル・マーケティングとして、各種講演や執筆活動を行っている。最近は、特にデータベースとクラスタリングに注力し、検証レポートを作成するのをライフワークとしている。
|
|

|
|
|