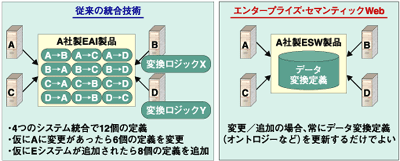|
||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||||
| 従来の統合技術/統合製品との違い | ||||||||||||
|
前回はセマンティックWebが研究分野だけではなく、エンタープライズの世界でも使われはじめていることを解説してきた。それには従来の統合技術に限界が見えてきたからだ。しかし先進的な企業は、成熟しているとは言い難いエンタープライズ・セマンティックWebを適用している。 既存の統合技術/統合製品との違いを端的にまとめると以下の3点に集約される。
表1:セマンティックWebと統合技術/統合製品の違い(再掲)
|
||||||||||||
| データ変換定義のノンプログラミングと局所化 | ||||||||||||
|
既存の統合技術/統合製品と比べ、まずノンプログラミングで対応できる範囲が広いことがあげられる。 既存の統合技術/統合製品(例えばEAI製品)でもノンプログライミングでデータ変換定義を行う機能はあるが、そのほとんどはメタデータレベルであり、インスタンスデータレベルの語彙や語彙と語彙の関係、ならびにその取り扱いルールは定義できない。場合によっては、プログラムとしてデータ変換ロジックをコーディングする必要もでてくる。 それに対し、エンタープライズ・セマンティックWebは、オントロジーを利用するため、それらを定義することも可能だ。既存の統合技術/統合製品より多くの関係を定義できるため、データ変換に関する定義を分散しなくてもよくなる。 つまり、データ変換に関する定義情報を局所化することができるのだ。仮にシステムの拡張や更新に伴ってシステムやデータフォーマットを追加・更新する場合も、局所化されているデータ変換定義さえ追加・更新すれば対応きるようになる。 |
||||||||||||
|
1 2 3 次のページ |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||