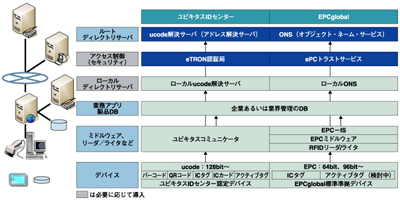|
||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| EPCとucode〜競合か共存か | ||||||||||
|
次に技術面での懸案事項もある。モノに付与するIDは、EPCかucodeのどちらのコードを利用すべきか、システムアーキテクチャとしてはEPCグローバルとユビキタスIDセンター(T-Engineフォーラム)のどちらを採用すべきであるかという点である。 両者のシステムアーキテクチャはインターネットを活用したオープン領域での利用が可能である点や、IDに基づいたアドレス解決(DNSのような機能を用いて、商品情報サーバの検索)を行えるなど類似性が高い(図1)。 また、これまで関与した実証実験に関しては検証目的が異なっていても対象業態が類似していることや、米国発のEPCグローバル、日本発のユビキタスIDセンターということもあり、対立の構図で描かれることが多いのが現状である。 なお、EPCグローバルの活動拠点は日本にもあり、国内の取りまとめは関しては財団法人流通システム開発センターが、研究機関であるAuto-IDラボの研究メンバーとして慶應義塾大学が関与しており、決して米国中心の活動ではないことを断っておく。 しかしながら、詳細に見比べれば両者には大きな違いがある。IDのコード長はEPCが96bit(64bit版もある)から、ucodeは128bitからの構成となるほか、ucodeはメタコード体系をとるため、EPCをも包含可能な設計となっている。また、ユビキタスIDセンター側は媒体(デイバス)として2次元コードやICカードを対象とすることや、ユビキタスコミュニケータという端末を有する点などである。 そのほか、EPCグローバルは流通に関わる世界的な業界団体であるGS1傘下の組織であるため、EPCは商品コードに利用されているGTIN(国内で利用されているJANコードは2005年以降、GTIN:Global Trade Item Numberに移行中)の個品管理用として利用されるSGTIN(Serialized Global Trade Item Number)、SSCC(Serial Shipping Container Code)、SGLN(Serialized Global Location Number)用に利用され、サプライチェーンでは標準的に利用されることが想定されている。 このように、両者のシステムアーキテクチャの類似性はあるが、サポートする業界団体の有無や対象とするデバイスの違いなど、技術面だけで判断できない要素もある。そもそもオープン領域において、雑貨などの消費財へユニークなIDを付与してモノを管理するアイテムタギングの実現時期がすぐには訪れないこともあり、RFID利用が本格普及するまではEPCとucodeの実質的な競合状態は発生しないと思われる。 |
||||||||||
| 将来的にはインターオペラビリティの確保を | ||||||||||
|
では、オープン領域での利用が本格化し、RFIDタグが何にでも付与され、社会インフラとしても利用されるユビキスネット社会が到来するとどうなるだろうか。 現在でもバーコード用のコードは業界レベルで、あるいは企業独自で発行・管理されており、RFIDでモノを管理する時代が到来したとしてもすべてのモノがEPCあるいは、ucodeのいずれかで統一されると断言はできない。また消費財の生産・製造拠点として重要な位置を占める中国がRFID用コードの独自標準を検討しているとの話題もあり、今後の動向が気になるところである。 システムアーキテクチャの標準化の観点では、将来的には商品の生産から販売に至るサプライチェーンではEPCで商品管理を行い、商品購入後はユビキタスコミュニケータを用いてトレーサビリティ情報を閲覧したいというシーンも想定されるだろう。 このような際に、商品情報を提供する情報システムがEPCに準拠して構築されていたために、ユビキタスコミュニケータでアクセスできない、あるはコンテンツを閲覧できない可能性がある。この場合、企業間取引用EPC対応で、コンシューマサービスはユビキタスID対応という2重の投資が発生する。 両組織の提唱する技術は現在のところ国内では検討段階にあり、その状況で技術的優劣を問うこと自体にはあまり意味がない。両者の市場への参入アプローチも異なるほか、EPCとucode以外のRFIDコードが出現する可能性もある。 今後、技術面において注意すべき点は、これら複数のコード体系が存在した状態でも、上位側の情報システムにおいて相互アクセスと参照が可能か、標準かつ汎用的な技術をもちいてコンテンツが開発されているかなどがポイントになるかと思われる。 |
||||||||||
|
前のページ 1 2 3 次のページ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||