| ||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||||||
| mtコマンドによるテープ装置の制御 | ||||||||||||||||||||||
今はもうハードディスクレコーダーが全盛ですが、昔ビデオデッキを使用していた際に、大切なテープの上に誤って上書きしてしまった事はありませんか?例えば、120分のビデオテープの前半60分に第1回のドラマを録画していて、その後に第2回を録画しようと思った時に、間違って巻き戻されていて、まだ見ていない第1回に上書きしてしまったなんて経験があります。ビデオデッキの場合には、事前に内容を目で見て確認することもできますが、バックアップ用のテープ装置の場合には内容を見ることが難しいです。 そこで、活躍するのがmtコマンドと、テープのEOFマークです。 まず、テープの一番先頭にはBOT(Beginning of Tape)というマークが置かれ、最初の位置を示すようになります。そして、データが書かれた後には必ずEOF(End of File)マークが置かれます。データとEOFを書き終わった段階で、使用したデバイスファイルが「/dev/st0(rewind)」のタイプであった場合には、テープヘッドは先頭に戻ります。「/dev/nst0(no rewind)」を使用している場合は、図1のようにテープヘッドはその位置で停止しています。 | ||||||||||||||||||||||
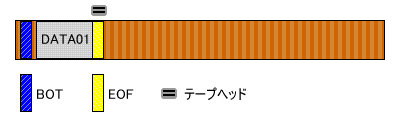 図1:EOFマークとテープヘッダの関係 | ||||||||||||||||||||||
| mtコマンドは以下のようなコマンドに表2のオプションを付けて実行します。詳細なステータスを確認できたり、巻き戻しや早送りなどの機能があります。 | ||||||||||||||||||||||
# mt -f /dev/st0(または/dev/nst0)操作内容 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
表2:mtコマンドの主なオプション | ||||||||||||||||||||||
| 最初に、mtコマンドのステータスを使用して、現在の状況を確認します。場所を確認するのには、File numberの数字を見るようにしてください。番号0がテープの先頭になります。 | ||||||||||||||||||||||
# mt -f /dev/st0 status | ||||||||||||||||||||||
次に、テストデータを作成し、tarコマンドを使用して(詳細な使用方法は後述します)ファイルを1つ「/dev/nst0」(no rewind)でバックアップしてみます。mtコマンドによって確認してみると、File numberが1となっており、ヘッドの位置が移動していることがわかります。 | ||||||||||||||||||||||
# touch /tmp/testfile | ||||||||||||||||||||||
EOFはEnd of Fileの意味であり、本来はファイルの終端を示すものですが、同時に連続で書き込む際には、次のファイルの先頭を示すことになります。図2をよく理解し、間違った場所への書き込みは避けなければなりません。 試しに、同じようにDATA02〜04をバックアップすると、File numberは4番目になりました。 | ||||||||||||||||||||||
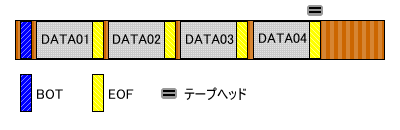 図2:連続したバックアップ | ||||||||||||||||||||||
# mt -f /dev/nst0 status | ||||||||||||||||||||||
ここで、もしDATA03をリストアしたいという場合にはどうしたらよいでしょうか?具体的にはFile numberが2番になれば、DATA03の先頭にテープヘッドが移動することになります。単純にbsfオプションを使い、2つ戻ればよいような気がします。しかし、bsfはDATA03の手前のファイルマークではなく、データそのものの第1ブロックに移動してしまいます。その様子は、最終行でEOFが検出されていないことからもわかります(図3)。 | ||||||||||||||||||||||
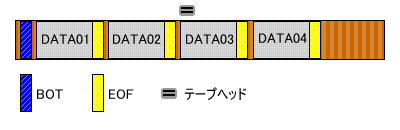 図3:誤ったテープヘッダの位置 | ||||||||||||||||||||||
# mt -f /dev/nst0 bsf 2 | ||||||||||||||||||||||
正しくは、bsfmコマンドを使用し、その地点を含めたEOFの数戻るという操作をします(図4)。 | ||||||||||||||||||||||
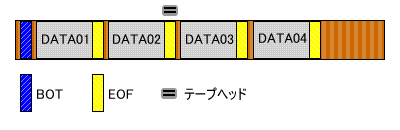 図4:正しいテープヘッダの位置 | ||||||||||||||||||||||
# mt -f /dev/nst0 bsfm 3 | ||||||||||||||||||||||
mtコマンドを使用する際には細心の注意が必要です。本格的な運用をする際には、テスト用に使用してもよいメディアを用意し、何度もテストしてみるのがよいでしょう。 このような煩雑な作業は、商用のバックアップソフトウェアを使用することで、すべてGUIで操作が可能であり、リストアしたいジョブの選択が容易になります。 | ||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||

















