| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成果主義の実態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
終身雇用と年功序列の下で、日本企業の最大のコア・コンピタンスは企業文化の共有であった。従業員の価値は勤続年数で決まっていた。日本の人事政策も、勤続年数に応じて、従業員が恩恵をこうむるしくみになっていた。給与は勤続年数に応じて高くなっていく。 勤続年数に応じた会社の住宅融資制度や教育融資制度により、従業員は自分や家族の将来設計を立てていった。会社の業績が良くなっていけば、自分達の人生も必ず良くなると、従業員は信じていた。企業戦略と従業員の行動が、終身雇用と年功序列の制度で見事に一致していた。 しかし、長引く不況とグローバル化の影響により、日本型経営の根幹である「終身雇用と年功序列の運用」が機能しないと、多くの経営者は判断するようになってきた。経営不振を理由に工場は閉鎖され、中高年を中心にリストラの嵐が吹き荒れた。その結果、1990年代から、多くの企業が日本型人事政策に代わるものとして、「成果主義」を導入した(表1)。成果主義のコンセプトは、「仕事でどのような成果を上げることができたか」を重要視する人事制度である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表1:成果主義の実態 出典:溝上憲文 「隣の成果主義」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図4は日本能率協会が発表した成果主義導入について、全国の上場企業及び非上場企業の経営者に対する調査報告である。これによると、全体の83.3%の企業が、人事制度として成果主義を導入いている。その目的として、社員の意識改革や、年功制度の脱却を上げている。しかし、70%以上の企業が現行の成果主義に満足した結果を得られず、修正を検討している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
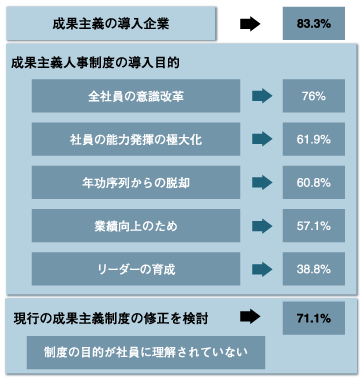 図4:成果主義人事制度導入の調査結果1 出典:日本能率協会「経営課題に関する意識調査及び成果主義に関する調査」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
労政行政研究所の発表も同様の結果である(図5)全体の70.1%が成果主義を導入している。そのうち、自社の成果主義人事制度に問題ありとの回答が、経営側では88.2%、労働側では93.8%に達した。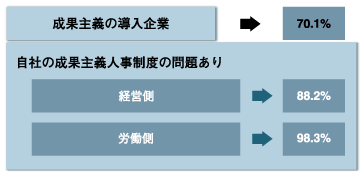 図5:成果主義人事制度導入の調査結果2 出典:労政行政研究所(2005年3月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成果主義の失敗事例はマスコミでも数多く取り上げられいている。成果主義導入によって、6月の手取額が22,000円になり、東京地裁に訴えられらケースやベストセラーになった「虚妄の成果主義」など、例をあげればきりがない。 人事政策には企業文化を形成していく役割がある。企業戦略を達成するためには、異なる価値観を持った従業員に対して、価値観を共有する為の人事制度を与えることが必要になる。このことは、演奏者に同じ楽譜を配られて、初めてベートーベンの第五楽章やショパンの英雄ポロネーズが奏でられることと、同じである。各自が自分勝手に演奏しはじめたら、協奏曲にならない。 企業文化は、その国の文化や歴史的背景に多く関係してくる。従って、根本的な考え方や価値観の違いを検証することなしに、欧米のうわべだけの制度を導入してもうまくいかない。また、経済環境や社会環境が変われば、昔のままの、制度をそのまま運用していっても、うまくはいかない。人事政策も環境に合わせて進化させていかなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次回は | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年功序列下では、人材価値の可視化は簡単であった。企業にとって、「勤続年数」こそが人材価値そのものだったからだ。それでは、「勤続年数」に代わる、能力評価を欧米諸国ではどのように行なっているのだろうか。次回は欧米の人事制度と、人材価値の可視化の為に、人材情報システムでしか成し得ない役割について述べてみたい。欧米企業を中心とするERP(Enterprise Resource Planning)のようなデータの統合システムがなぜ現れたかの理由もここにある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||



















