| ||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料ソフトは全て「商用ソフト」なの? | ||||||||||||||||||||||||
でも、Linuxってよくわかんないんですよ。会議でも金子さんが、LinuxサーバはRed Hat Enterprise Linuxは高いから止めてDebian GNU/Linuxにしましょう、なんて言ってたんですけど、Linuxってたくさん種類があるみたいでよくわかんないですよ。 Windowsでいう「なんとかエディション」みたいなものですか? タダから高いのまでいっぱいあるし。 もとのぶ先生 うーん、それはちょっと違うかなぁ。森くんはLinuxの歴史って知ってるかな。 LinuxはLinus Tovalds氏っていう人が学生の時に作成したのがはじまりだけど、実際にLinus氏が作成した「Linux」は、OSの中核をなすカーネルという部分だけで、これじゃ一般人は使えない…… 金子さん でも、逸汎人なら…… もとのぶ先生 はぃはぃ、金子さんみたいな人なら大丈夫ですね。 で、さまざまなプロダクトを集めて、OSとして使える形にしたものをディストリビューションと呼ぶようになったんだ。 最近ではLinuxというとLinuxカーネルというより、Linuxディストリビューションの意味でとらえる人が多いね。ところで、ディストリビューションって英語でどういう意味? 森君 あー、「分散」とか、ですよね。 もとのぶ先生 そういう意味もあるけど、「配布物」という意味もある。 ディストリビューションと呼んでいる由来は、Linuxの黎明期にLinuxカーネルとさまざまなプロダクトを集めてUNIX互換OSとして使用できる形にして配布してたんだけど、それを「配布物」の意味でディストリビューションと呼んでいたからなんだ。 主要なプロダクトはみんなオープンソースだったから、だれでもディストリビューションを作れたし、どのプロダクトのどのバージョンを含めるか、デフォルトの設定をどうするかといった所もみんな自由に工夫できた。で、いろんなディストリビューションが誕生したし、いまも誕生しているんだ。 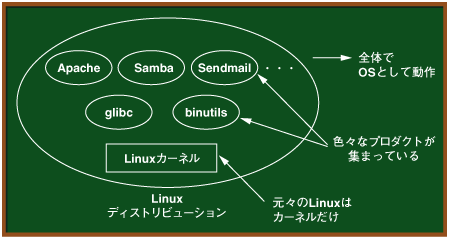 図3:さまざまなディストリビューションがLinuxには存在している 一口にLinuxといってもさまざまなディストリビューションが存在しているのは、オープンソースならでは、かもね。 もとのぶ先生 うーん、それは残念ながら違うかな。 Linuxカーネルにもバージョンがあるから、ディストリビューションが採用しているバージョンによって動いたり動かなかったりってことはあるし、動かすのに別のプロダクトが必要ってソフトも多いから、ディストリビューションに含まれているプロダクトによって、動いたり動かなかったりってこともある。 ま、森君も、無料のディストリビューションをひとつ触ってみるといいんじゃない? 森君 そんなに言うんだったら、CD-ROMやDVD-ROMで起動できるやつだったら、ちょっと試してやってもいいかな。 金子さん 「試してやって」というのは…うーん、だったらKNOPPIXやUbuntuあたりはどう?どちらもわたしオススメのDebian GNU/Linuxを元に作られているディストリビューションで… 青井部長 はいはい。金子さんが、オープンソースやらLinuxやら、すとーるまん様に注ぐ情熱と知識の1%でも、本来の仕事に使ってくれたらねぇ…(しみじみ)Linuxではともかく、そのうち仕事で森君に抜かされますよ。 金子さん ひ、ひど〜い!(泣) 青井部長 だって、昨日頼んでおいた見積もりだって、いまだにできてないんでしょう? 森君の議事録の方が、先に上がってきそうですよ。 一同 ははははは…!(次回に続く) 本記事はフィクションであり、実在の人物には一切関係ありません。 | ||||||||||||||||||||||||
| なぜなにオープンソース ここでは、読者の方から頂いた質問をたかはしもとのぶ先生がお答えします。 Q: OSSを用いた業務のコンサルティングなどのサービスを行う業者は、そのサービスを行う上で利用するOSSの開発者に対して許可を求める必要はあるのでしょうか。(例えば連載第一回にあったDebianをサポートする業者は、Debianの開発者に対して許可を求めたり対価を支払ったりしているのでしょうか?) OSSにもいろいろライセンスがあるようですが、学術プログラムなどではインターネット上にソースを公開していて、ドキュメントに「著作権は放棄していない」と書いていても、具体的にどのライセンスに準拠すると書いていないものが多くあります。このようなプログラムのサポートを業務として行う業者は、プログラムの開発者に対してどのような義務を負うのでしょうか? たかはし先生からの回答 A: 一般的なライセンスはプログラムの利用や使用に関する規定を行っています。プログラムの「サポート」や「サービス」は、利用、使用のいずれにも該当しませんので、わたしが知る限り、義務が発生することはないと思います。 なんらかの義務が発生するのは、プログラムの利用もしくは使用に対してとなります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||

















