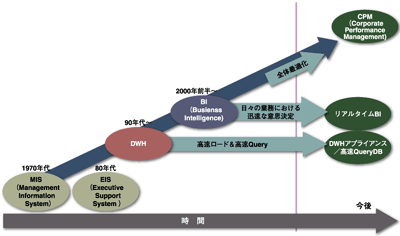| ||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| BI今後の展開 | ||||||||||
MIS、DSS、EIS、SISといったキーワードが姿を消した一方で、現在も生き残り、なおかつ更なる進化を遂げようとしているのが、90年代に提唱されたDWH(Data Warehouse:データ・ウエアハウス)とBIである。DWHとBIのこれまでの進展と今後の方向性を図2に示す。 DWHの進化の方向性の1つはリアルタイム性の強化である。これはアクティブ・ウェアハウスと呼ばれ、NCRのTeradataがいち早く製品化している。もう1つのDWHの方向性はDWHアプライアンスと呼ばれる、低コストかつ高パフォーマンスを売りにした新たな製品カテゴリの登場である。こうしたDWHの進化については次回以降に詳しく解説する。 またBIについても、大きく2つの進化の方向性が見えてきている。1つが「リアルタイムBI」と呼ばれるリアルタイム性を追求したBIの登場である。現在のBIは、業務アプリケーション用のデータベースからある時点のデータを抽出し、多次元データベースを構築し、そのデータを対象に分析や集計を行うという仕組みになっており、リアルタイム性に乏しいものとなっている。このようなBIは中長期の予算計画を過去数年の実績を元に立案する場合や、4半期決算のために過去3ヶ月の売上実績などを集計し、分析を行うといった場合には特に問題にならない。 しかし現在のビジネススタイルでは、こうした過去のデータを対象としたBIのスタイルがそぐわないケースがでてきている。Amazon.comのようなeビジネスを展開する企業では、顧客行動や在庫情報などを極力リアルタイムに近いタイミングで収集し、分析する必要があるだろう。この「リアルタイムBI」についても、次回以降に詳しく解説する予定である。 もう1つのBIの方向性は、これまでマーケティング部門や経営企画部門など部門毎に最適化され構築されてきたBIを、全体最適という観点から全社規模での戦略的な活用を目指す「CPM(Corporate Performance Management)」というキーワードに象徴されるものである。今回はこのCPMについて解説する。 | ||||||||||
| CPMとは | ||||||||||
企業がビジネス環境の変化に迅速に対応していくためには、意思決定のスピードをできるだけ早めることが求められる。そのためには、自社の現状を可能な限り正確に把握しておく必要があるため、高品質かつ網羅的な情報が収集されている必要がでてくる。このように企業の競争力強化のため、経営判断に必要な情報をもれなく収集し、戦略的に活用していこうという取り組みから生まれたのがCPMである。 もともとCPMは米国の調査会社であるGartnerが提唱した用語である。同社ではCPMを「企業がビジネス・パフォーマンスを監視および管理するために使用するプロセス、方法論、評価基準、システムを指す包括的な用語である」としている。 CPMは大手のBIベンダーが現在、最もマーケティング上注力している領域であるといえるが、ベンダーによってはCPM以外にもEPM(Enterprise Performance Management)、BPM(Business Performance Management)など異なる呼び方をしている。例えば、コグノスやオラクルはCPM、ビジネス・オブジェクツはEPM、ハイペリオンやSASはBPMという具合だ。しかしこれらに本質的な違いはなく、同じ概念を指すと思ってよい。なおここでいうBPMはビジネス・プロセス・マネジメント(BPM)と混乱しやすいので注意が必要である。 CPMは先に解説したようにこれまでのBIを含め、バランス・スコアカードやシックス・シグマ、ABC(Activity Based Costing:活動基準原価計算)などの方法論や予算計画、戦略策定などのプロセスから構成される非常に包括的な概念であることから、その本質を見失いがちである。特に一般的な認知度がそれほど高くない現状においては、ビジュアル的にわかりやすいこともあってCPMというとバランス・スコアカードでKPI(Key Performance Indicator:主要業績指標)を管理し、ダッシュボードを構築することであるという誤解も見受けられる。 確かにこれらはCPMを構成する重要な要素であるが、CPMそのものではない。CPMの本質とは、経営目標に基づいて策定された戦略、実行計画、予算を達成するために、日常のオペレーションレベルのデータをフィードバックし、進捗が遅ければ加速させたり、方向性が間違っていれば修正するなど計画と行動を修正するためのPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを徹底することである。 | ||||||||||
| CPMの実現ステップ | ||||||||||
CPMにおけるPDCAサイクルを考える場合、一般的には次のような4つのステップから構成される(図3)。 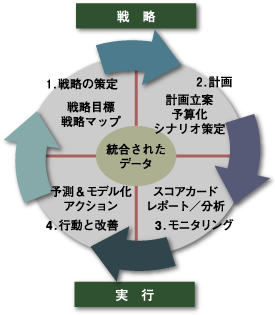 図3:CPMの実現ステップ | ||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||