| ||||||||||||||||
| 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||
| BIツールの高度化が進む時代 | ||||||||||||||||
最近のIT業界の営業マンやツールベンダーの話から判断すると、相当数のBI(ビジネスインテリジェンス)ツールが売れたことは間違いないようだ。 だが、ユーザ企業側からは「ツールを買っただけで社内にサービスを提供できていない」「大量のライセンスを購入したものの実働はその数割程度」という声も聞かれる。熱しやすく冷めやすい、日本人の典型的な姿を見る思いがするが、BIツールを使いこなす難しさも起因しているように思う。 一般にBIといえば、高度な演算や関数処理といった情報処理を施し、ビジネスの隠れた実態を白日の下にさらけだすような使い方を指す場合が多い。 ただし、こうした高度なデータ処理のニーズはマーケティングやR&Dの部署ぐらいなものだろう。その他の多くの部門では、クロス集計表をコツコツ作成しているのが現実ではないだろうか。 だが、それでもなおBIツールは機能拡充され続けて高度になっていく。 そのため、もしかすると我々利用者はとてつもなくプアな仕事をやっているのではないか、ツールに置いてけぼりにされているのではないか、と不安を抱く方もいるかも知れない。 実は筆者もBIを担当して10年近くになるが、同じように悩んだ時期がある。当社で使っているBIツールは販売ランキングの上位には決して顔をださないような代物で、導入の対象もセールス部門への配備が中心だった。 当時、セールス部門が毎月クロス集計表を印刷している姿を見て、「もっと先進的なBIツールを導入して現場の意思決定を革新させなければ」と思ったものだ。 だが、こうした「先進的なBIツール」は格段に値が張る。1ユーザライセンスが20万円を超えるのは当たり前で、全社に配備すると1,000万を軽く超えてしまう。こうした「1,000万円ツール」で相変わらずクロス集計表作りを繰り返すだけであれば、コストパフォーマンスは著しく劣り、経営陣から大目玉を食うに違いない。 | ||||||||||||||||
| 情報活用の成熟度に応じてBIツールを選定する | ||||||||||||||||
こうしたことから考えると、「BI導入のポイント」は高度なツールを使いこなすということではなく、データを使って日常業務を論理的に判断していく、という考えに行き着く。つまり各業務において、経験や勘、度胸といったKKDから脱却し、データを活用した客観的判断の領域にシフトすることに意義があるということだ。 そのうえであれば、該当する個人や組織、情報活用のレベル(図1)や難易度によって、選択する道具が変わってくることも理解できるだろう。 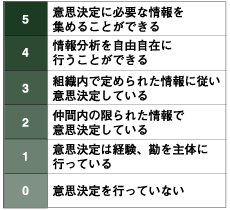 図1:情報活用の成熟レベル(有田式) 例えば、従来からまったくデータを活用していない個人や組織に対して、重回帰分析を中心とするBIツールを導入したとしよう。最初は、摩訶不思議なデータに興味を示すかもしれないが、単に面倒さと難しさだけが気持ちとして残ってしまい長続きはしないだろう。 こうした場合には、むしろ日々の活動状況をデータで見ることが、いかに大切かを認識させることが重要だ。活動を可視化し、また判断の精度をあげるためには、どういったデータが必要なのかを見い出し、認識させるところからスタートするわけだ。 そして、データの表現方式もクロス集計表や簡便なグラフなどを使って習慣として定着させていく。その際には、基本的なデータベースの整備と、簡便な検索ツールを用意することになるが、豊富な機能を有するよりも、簡単に取り扱える点を重視する必要があるだろう。 かたや、日々データを蓄積しながら、クロス集計表で基本的なデータが押さえられているものの、それ以上の発展性が見られない企業もあるだろう。この場合は、データ加工の効率化と活用の視点でツールを選択する。 また指標は同じでも、キー項目だけが異なるような集計表を沢山作っている場合もある。その場合は、OLAPのように簡単にキー項目を変えられる仕組みが有効だ。グラフ化や関数処理の効率化を目指すのであれば、専用のBIツール、もしくはExcelにアドインプログラムを付加して自動化ニーズを満たす手もある。 一方、情報活用を促進させるためには、習慣化・義務化によって硬直してしまっている、データ活用状況をワンランク上に持ちあげる工夫が必要となる。 具体的には、市販のExcel活用本などに載っている、データ分析事例の応用を試みてみることだ。意外に、ABC分析(注1)やポートフォリオなどを使っていないことが多いのに気付くだろう。そのかわりに、例えば小売業ではRFM分析(注2)が判断の基本になっていたりする。 ※注1:ABC分析 商品や顧客などを重点管理するために用いる用法。金額の多い順に並べ、累計額をパレート図として表現する。構成比の順にA・B・Cの3ランクに分け、各ランクの特徴を把握するための基本ツールだ。 ※注2:RFM分析 一般消費財の購買動向を把握するために用いる手法。最新購買日・累計購入回数・累計購入金額を分析対象とし、各企業独自のセグメント分けやランク付けによって顧客を分析する。データベースマーケティングでは、顧客データ分析のもっとも基本的なものの1つ。 さらにマーケティング部門など、既にデータを高度に分析している場合は、オペレーションの効率化と精度向上を主眼としたソリューションを検討することになる。大量のデータから即座にデータを抽出する機能や、データマイニング機能、OLAP機能、豊富な統計解析メニューなどの類だ。 これらの機能がなければ、競合他社に打ち勝つことができないため、企業は高額な投資もいとわない。またこれにあわせて、主要ベンダーは最新で高度な機能を盛んにアピールすることとなる。 こうしてみると、クエリをユーザ自身が定義できる機能や日本地図を表示させる機能、複雑なレポート作成機能など、メーカが差別化の一環として謳う高度な機能が必要となるのは極めて限られたケースだとわかる。 ところが、ユーザ企業は「ひょっとしたら将来必要かも知れない」と期待して、不必要な機能まで買ってしまい、結果として持て余してしまうことが多いように思う。 情報の活用段階というものはツールではなく、人間の仕事の進め方や感性に大きく依存しており、年単位の進歩になってしまう。つまり、1〜2年の短期間で償却できる導入・展開モデルを想定しておくことが極めて重要だと筆者は考える。 | ||||||||||||||||
| 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||



















