|
||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| サーバ仮想化について | ||||||||||
|
サーバ仮想化は数年前までエンタープライズサーバでしか実現できなかった機能です。近年、IAサーバを使ったサーバ仮想化が注目を浴びています。テクノロジーの進化により安価なサーバでも仮想化が行えるようになったためです。 テクノロジーの進化によりインフラは整いました。しかしながら、サーバ仮想化に対応できる技術者の数は不足しています。仮想サーバを使うだけならば簡単ですが、いざ構築となると仮想化の考え方を理解している必要があります。 そこでまず今回は、仮想マシンとサーバ仮想化について解説します。 |
||||||||||
| 仮想マシンとは | ||||||||||
|
まず仮想マシンとは何でしょうか。仮想マシンとは仮想化技術によって物理的なコンピュータを分割し、その中で独立したOSを持って動作する論理的なコンピュータのことをいいます。簡単にいえば1台のコンピュータで2台以上のOSを動かすことです(図1)。 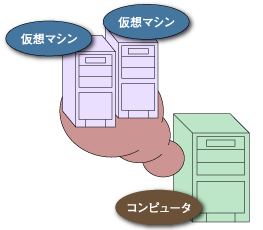 図1:仮想マシンのイメージ 仮想マシンを作るには仮想マシンソフトウェア(ファームウェア含む)が必要となります。仮想マシンソフトウェアには大きく分けて以下の3つのタイプの実装方法があります。
表1:仮想マシンソフトウェアのタイプ
|
||||||||||
| 仮想マシンソフトウェアのタイプ | ||||||||||
|
それでは表1にあげた仮想マシンソフトウェアの3つのタイプについて解説します。 |
||||||||||
| ファームウェアタイプ | ||||||||||
|
ファームウェアタイプの仮想マシンは、IBM社のUNIXサーバに搭載されているLPAR(Logical Partitioning)、HP社のUNIXサーバに搭載されているvPars(Virtual Partitions)が有名です。 しかしファームウェアタイプの難点として、CPUはソケット単位、デバイスはPCIスロット単位でゲストOSに割り当てないとならないなどの制限があります。 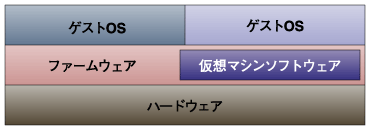 図2:ファームウェアタイプの仮想マシンソフトウェア |
||||||||||
|
1 2 3 次のページ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||


















