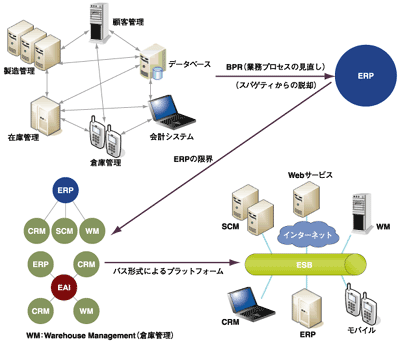| ||||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||
| 今日のSOA/ESB | ||||||||||||||||||
「インテグレーションはSOAに基づいて実施し、そのベースとなる基盤にESB(エンタープライズサービスバス)を採用することが、現時点で考え得るもっとも効果的な方法である」というのがSOAベンダー各社の一致した見解となっています。 ところが、各ベンダーで一致しているかのように見える「SOA」や「ESB」は、アプリケーションをインテグレーションするという、大枠の考え方を示しているにすぎず、規格として定まったものではありません。そのため、SOA/ESB関連製品は各ソフトウェアベンダーの解釈によって異なる仕様となっており、各ベンダーが唱えるSOAの設計方法(モデリング)や具体的なSOA実装方法もまた異なっているのです。 そこで本連載では、SOAやESBのコンセプトとは本来どのようなものであるか、またSOA/ESB製品がどのような機能を備えておくべきかを考察していきます。第1回では、SOA実行基盤であるESBがなぜバス形式を採っているのか、その理由を考えます。 | ||||||||||||||||||
| ESBの「B(バス)」が意味するものとは | ||||||||||||||||||
ESBやSOAは、アプリケーションをインテグレーションするための技術であり、製品です。ESBを正しく理解するためには、まずこのインテグレーションがどのように推移してきたか振り返ってみる必要があるでしょう。 | ||||||||||||||||||
| ポイントツーポイントのインテグレーションスパゲティ | ||||||||||||||||||
企業のITシステムは、その企業の実業務を支援するために構築されてきたという経緯があります。 当初は業務内容に応じ、営業システムや顧客管理システム、会計システム、製造管理システムなどを個別にまたは企業の部門組織ごとに構築することが普通でした。また個々のシステムの特性に応じて、採用するハードウェアやOS、開発言語をその都度アドホック(個別に)に選択してきました。 個々に構築され、それぞれが独立して運用されている中で、システム間でデータを共有したいという要求が当然のこととして発生してきます。例えば、営業システムと顧客管理システムとの間で顧客情報を共有したい、営業システムで管理している注文情報を製造管理システムに送って生産計画の作成に利用したい、といった要求が考えられます。 そこで、異なるハードウェアやOSに基づいたシステム間でデータインテグレーションを実現するために、様々なIT技術が生まれました。以下はその一例です。
表1:データインテグレーションを実現する技術 このような技術に共通していることは、システム間を1対1でつないだ(ポイントツーポイントの)インテグレーションである点です。また、使用される技術もシステム間の特性に応じてその都度アドホックに選択されてきました。 その結果、異なるインテグレーション技術によって個々のシステム間を結んだリンクが複雑に絡み合っている、いわゆる「インテグレーションのスパゲティ状態」を招き、多大なメンテナンスコストを要するものとなっていました。 | ||||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||