| ||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||
| レベル3:定義 | ||||||||||||||
レベル3は組織間にまたがり、業務プロセスが定義された状態です。組織の業務機能が整った状態ですので、ビジネスプロセスの可視化をなされた状態としてのBPMの最初の到達点でもあります。 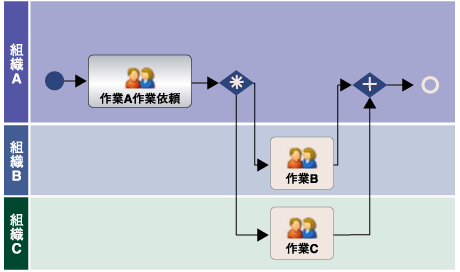 図5:レベル3の状態 レベル3では扱う対象が基幹システムおよびそこで扱うアプリケーション、データが含まれます。そのことは当然に組織をまたがった最適化目指します。 現状を見ますと、ビジネスプロセスが定義されていても、それと情報システムの連携がうまくいっているとはいえない企業が沢山存在しています。 顧客の窓口業務などは、情報システムの投入が直接サービスに繋がっており、その連携がうまくいっているケースです。しかし企業内の情報処理を見ますと、多くの場合は情報処理(データ投入)を1箇所に設けたり、実業務とデータ投入の仕事が分かれたりして、実業務と情報システムの内容の時間差があるケースがあります。また、情報システムが結果投入用に甘んじているケースも多くあります。 BPMの導入はビジネスプロセスの可視化と同時に情報システムとのインターフェースを決めていきます。つまり、業務プロセスと情報システムの最適設計を行うのがBPMSです。 確実に業務プロセスを定義して、そこで扱うデータおよびドキュメントを確定し、その処理の確実さを求める。そしてその延長線で情報処理との連携を持たせるのです。 これが内部統制や日本版法でビジネスプロセスが注目を集めている理由です。そしてBPMSでこの仕組みが実現すると、必然的にレベル4の環境が整ってきます。 | ||||||||||||||
| レベル4:管理 | ||||||||||||||
管理した状態はBPMSをビジネス層とシステム層に分けると、ビジネス層の完成形です。 企業の組織として統制がとれ、BPMSの配下で経営から事業推進、業務オペレーションまで連携がとれ、BPMSの機能を使い計画値/予定値と結果の比較が容易に行われています。 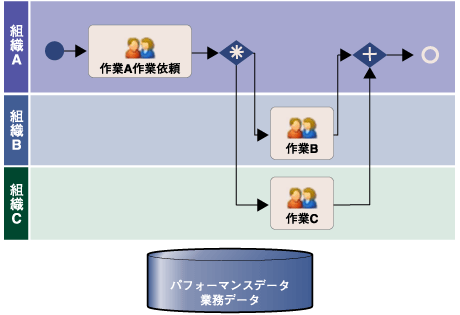 図6:レベル4の状態 BPMSはレベル4を実現する方法論を明確に提示しているマネジメントシステムであるといえます。マネジメントシステムの該当機能としては、プロセスの可視化(ワークフロー)/パフォーマンスデータの取得(BAM)/情報システムとの連携(BPELなど)/結果の提供などがあります。 | ||||||||||||||
| レベル5:最適化 | ||||||||||||||
環境変化に対応し、俊敏な経営の実現にはBPMSのビジネス層とシステム層のアーキテクチャに依存します。前回に解説しましたが、システム層はサービス基盤層と情報システム基盤に分かれており、ビジネス変化に影響されにくい情報システム基盤と、業務層との接点で再利用・汎用を実現するサービス基盤と設計構築が重要な成功要因となります。 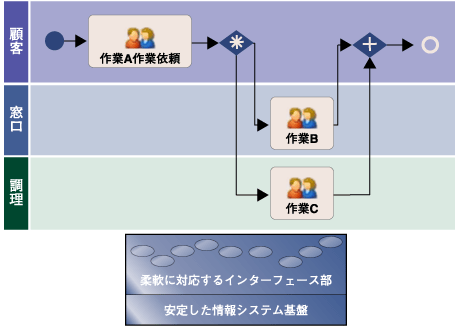 図7:レベル5の状態 | ||||||||||||||
| まとめ | ||||||||||||||
今回は、業務の成熟度をレベル分けして説明し、それに見合ったBPMの導入はどこにあるのかを解説してきました。最後に、企業にとってBPMの採用のポイントをまとめます。
表1:BPM採用のポイント | ||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||



















