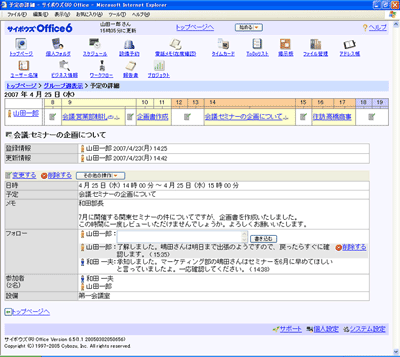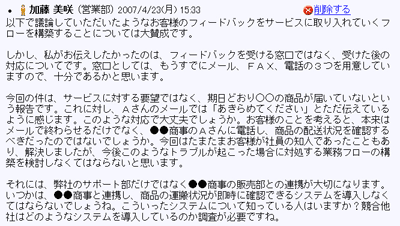| ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||||
| 社員全員に便利であると思わせることが大切 | ||||||||||||
「社員全員に便利であると思わせる」には、効果のでやすい「スケジューラー」のメリットを、まずは若手から中堅までの社員に体験してもらうことが大切だ。これらの社員は、キーボードやマウスでの操作に慣れており、この機能を使うことに対してほとんど抵抗はない。 むしろ電話受けや会議の調整などを行うことが多いので、同僚や上司のスケジュール、設備の空き時間を簡単に確認することのできる「スケジューラー」のメリットを直接的に感じることが可能だ。 しかし問題は、中堅以上の社員に使ってもらうということだ。よく聞く失敗は、若手の社員が積極的に自分達の予定をスケジューラーへ入力しようとしても、中堅以上の社員は利用しないことが多いので、結局社内で浸透せず、業務の効率化に結びつかないというケースだ。 1人でもグループウェアを使わない社員がいれば、その1人のためにグループウェア以外の紙やホワイトボード、電話などのアナログな方法でスケジュール調整を行わなくてはならない。これは、2度手間になるだけでなくコスト増にもつながってしまうので、グループウェアは浸透しない。 | ||||||||||||
| まずは若手社員に便利さを体験させること | ||||||||||||
そこで社内で実践していただきたいのが「スケジューラーで上司のスケジュールを自由におさえることができる」というルールをつくることだ。これにより、若手社員は会議のセッティングなどをスムーズに行うことが可能になるので、頻繁に使うようになる。 また上司は自分の予定をスケジューラーに登録しないと、部下に空いているとみなされ、どんどん予定を入れられるので、使わざるを得ない。ここで、中堅以上の社員が一旦スケジューラーを使いはじめると「便利である」ことが体験できるので、それからは進んで使うようになるのである。 このようにまずはグループウェアを社員に使わせる環境を作ることが大切だ。 | ||||||||||||
| グループウェアでよく起こる問題を回避するには | ||||||||||||
これまでに解説した第1条から第4条を実施することで、グループウェアの利用率は格段に向上する。 しかし、社内でグループウェアが浸透しはじめる頃は、様々な問題が起こることが多い。このような問題が顕著になれば、グループウェアに疑問を抱く人も必ずあらわれる。こういった状況を回避するため気をつけなくてはならないポイントが、これから解説する第5条の「グループウェア上で不毛な議論をさせないこと」と第6条の「短い文章で感情を伝えること」だ。 | ||||||||||||
| 第5条「グループウェア上で不毛な議論をさせないこと」 | ||||||||||||
社内でグループウェアが浸透すると、もちろんグループウェア上でのコミュニケーションが増える。今までは、スケジュール調整や内容確認など、大した内容でなくてもわざわざ電話したり、会って話す必要があったが、グループウェアを使うことにより、簡単にコミュニケーションがとれるので、活用度がます。 しかし、そうなると人はグループウェアに頼ってしまい、どんなことでもグループウェア上でコミュニケーションをとろうとする。これが大きなトラブルを招くことにつながるのだ。そこで重要なのが第5条の「グループウェア上で不毛な議論をさせないこと」である。 | ||||||||||||
| 大議論をさせない | ||||||||||||
特に気をつけなくてはならないのが、メンバーへ様々な情報を発信できる「掲示板」などの機能を使った議論である。語弊のないように補足するが、あるテーマに関してメンバーから簡単なコメントをもらうといった使い方であれば、まったく問題はない。 トラブルを招くのは各メンバーが掲示板に数十行にわたる意見などを書き、大議論を行う場合である。 このような場合、書く方も読む方も相当な時間を費やさなくてはならず、効率的ではない。実際に会って話し合う方がよほど効率的で、よいアイデアなども生まれやすい。 また、掲示板で議論を行う場合、いくら正しい日本語を使って書いても、文章に「堅さ」や「高圧的」な態度が目立ち、自分の思っていることが伝わりにくい。最終的には感情論につながり、議論自体が炎上してしまうケースがよくある。 そこでグループウェア上では大議論をさせないようにすることを勧める。ただ、そのような意識を社員全員にもたせるのは非常に難しいので、例えば「1つのコメントに10行以上は書き込んではいけない」などというルールを作ることが有効である。 実際にサイボウズでも、そのような意識をもってグループウェアを活用している。 | ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||