| ||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| はじめに | ||||||||||
ビジネスの現場で様々なプロジェクトを進める際に、計画達成の方法論として「PDCAサイクル」が重視される機会が増えてきています。このPDCAサイクルは、単に意識するだけではなく、社員が一丸となって実際にサイクルに沿って考え、行動する必要があります。 | ||||||||||
| PDCAサイクルとは何か | ||||||||||
PDCAサイクルとは、製品開発や業務プロセスを「PLAN(計画)→DO(実行)→CHECK(評価)→ACT(改善)→PLAN(計画)……」の手順で循環的にくり返すことで、継続的に品質や業務の改善、業績向上を行うマネジメント手法です。 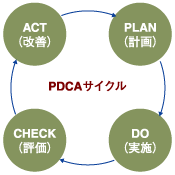 図1:PDCAサイクルの模式図 | ||||||||||
| PLAN(計画)フェーズ | ||||||||||
PDCAサイクルを実行するには、まず業務プロセスの現状を把握することからはじめます。このとき、目標と現状の間のギャップを埋める対策を「PLAN(計画)」として立案します。
表1:PLANフェーズで実行すべきポイント | ||||||||||
| DO(実行)とCHECK(評価)フェーズ | ||||||||||
そして次に、そのギャップを埋めるための対策を実際の業務プロセスで実行する「DO(実行)」の段階へ進みます。 続いて、実行した対策に問題がなかったかチェックします。これが「CHECK(評価)」の段階です。チェックされる側の視点を意識し「統制=コントロール」と受け取られないよう「できた」「できなかった」だけでなく、なぜそうなったかの背景や原因をマネジメントが一緒に考えることが大切です。 「評価」というよりは「確認」といったほうが理解しやすく、また次につなげることができるでしょう。
表2:CHECKフェーズを実行する重要なポイント | ||||||||||
| ACT(改善)フェーズ | ||||||||||
そうして得られた評価から、計画をそのまま進める個所と改善する個所について意思決定を行います。これも「統制=コントロール」にならないように、常に行動計画に立ち返り、計画の修正も含めて意思決定を行います。 行動計画は、こうすれば目標が達成できるはず、達成できる可能性が高まるという仮説であるという理解が重要です。これがACT(改善)の段階になります。
表3:ACTフェーズで注意すべきポイント | ||||||||||
| 繰り返しが重要なPDCAサイクル | ||||||||||
再びPLAN(計画)に移り、再び現状と目標を埋める対策を立案します。DOとCHECKは仮説の検証なので、行動計画は修正によって磨きがかかるという意識を持つことが大切です。 PDCAサイクルは「一巡」で終わるのではなく、再びPLAN(計画)に戻り、同じステップを何度も繰り返すところに特徴があります。こうすることで継続的にマネジメント能力を高めながら品質改善や業務改善・業績向上を実現していきます。この際に、行動計画への納得がない状態ではPDCAサイクルは回りません。納得度を高めるには、やはり対面によるコミュニケーションは欠かせないでしょう。 またPDCAは社員任せにしないことが重要です。本人の満足感だけが重視されてしまい、組織全体の視点が弱くなるため、マネジメントはより広い視点から社員1人1人のスキルに合わせ、アドバイスすることが必要です。 | ||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||

















