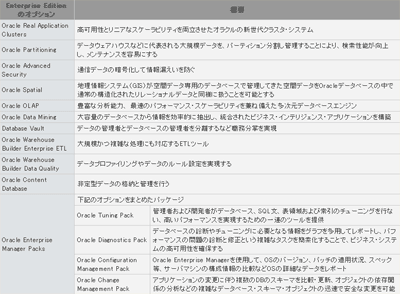|
||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| 意外と知らないオラクル | ||||||||||
|
この連載は、Oracle Databaseを、これから使ってみようという方に向けたものです。製品の成り立ちや試用版の入手方法、その使い方など、基本的なところを取り上げていきます。奥の深い製品ですから、学んでいただきたいことはたくさんあるのですが、まずは入り口として読者諸氏の一助となれば幸いです。 ITに関わる方であれば「オラクルという社名を知らない」ということは少ないかと思います。オラクルは、マイクロソフトに次ぐ世界第2位のソフトウェア企業であり、今年は創立30周年にあたります。そのイメージは様々だと思いますが、大半の方は「データベースの会社」として認識しておられるのではないでしょうか。 確かにオラクルは、世界で最初の商用リレーショナルデータベース(RDBMS)を開発し販売して成長した企業であり、現在でも主力製品であることに違いはありません。しかし最近ではデータベースに限らず、様々な角度から企業システムを支援するベンダーとなっているのです。 まずERPの分野では、すでにJ.D.Edwordsを買収していたPeopleSoftを買収し、これらを統合する作業を進めています。オラクルは買収前の時点でも、SAPに次いで世界第2位のERPベンダーでしたが、これらの買収によってさらに力を付けているのです。すでにSCMやCRMなどの特定の業務領域や、北米や欧州の一部ではSAPを超えているといった調査結果もあり、今後の動向にはますます注目が集まるところでしょう。 次にBusiness Intelligenceの分野では、Siebelを買収してOracle Business Intelligence Enterprise Edition(BIEE)を作成し、それまでのOracle Discovererを「Oracle Business Intelligence Standard Edition(BISE)」として販売しています。拡張性と可用性に優れたOracle Databaseに対し、データウェアハウスと業務データを一元化できる強みに加えて、異種データベースのデータを統合して分析できるオラクルは、BIの分野でも爆発的な成長を遂げている企業なのです。 さらに非定型データ管理も一元管理できるOracle Databaseの強みを活かし、コンテンツ・マネージメントの分野にも注力しています。この分野では単に非定型のデータを格納するだけではなく、企業データを横断的に検索できる「Secure Enterprise Search」も開発しました。データベースやメールサーバはもとより、社内のイントラネットやグループウェア、ファイルサーバの内容まで統合検索できるアプリケーションです。 |
||||||||||
| Oracle Databaseとは | ||||||||||
|
先ほど紹介したように、Oracle Databaseはいまや単なるRDBMSとは呼べなくなっています。OLAPで用いられる多次元データベースや分析用のマイニングエンジン、非定型コンテンツ、XMLデータの管理など、様々な機能を備えた統合データベースといってもいいでしょう。現在の最新バージョンは10.2で、製品名称は「Oracle Database 10g Release 2」となります。 世界的にもっとも多く使われているデータベースであり、そのシェアは半数近くを占めているのです。
Oracle is the #1 Database
http://www.oracle.com/database/number-one-database.html オラクルというと高価で大規模なシステム向けというイメージも強いようですが、実際には中堅中小規模のシステムでも多数使われています。その理由は、Oracle Databaseの製品構成を見れば、自ずと理解していただけるでしょう。 |
||||||||||
| Oracle Databaseの製品構成 | ||||||||||
|
Oracle Databaseは、3つの主なエディションと、オプション製品で構成されます(表1,2)。
表1:Oracle Databaseの製品構成 このほかにPersonal EditionとLiteが存在していますが、ここでは除外して話を進めます。Oracle Databaseの製品構成のなかでも注目していただきたいのは、2CPUまでのサーバに適用できる「Standard Edition One(以下、SE1)」の価格が、1ユーザあたり18,600円と非常に安価である点です(注1)。
※注1:
Intel/AMD製のプロセッサの場合。SE/SE1の最低ユーザ数は5ユーザでEEの場合は25ユーザ
Oracle Database 10gとともに登場したSE1によって小規模なユーザで利用するシステムにも、Oracle Databaseを採用しやすくなりました。このため近年の調査では売上高100億円以下の企業向けの市場でも、Oracle Databaseの採用率が非常に高まっていることがわかっています。また4CPUまでのサーバに適用できる「Standard Edition(以下、SE)」は、後ほど紹介するRAC(Real Application Clusters)が標準で装備されるという特徴があります。 本来Enterprise Edition(以下、EE)だけにオプションで提供されるRACが、総CPU数の制限があるとはいえ標準で利用できるのですから、可用性を担保する必要のある中規模システムにとっては非常に有意義です。すでに世界で10,000近い数の稼働実績を持つRACは信頼性も高く、他社にマネのできない優れたテクノロジーであるため、中堅企業でも採用が相次いでいます。 現在日本オラクルで行っているキャンペーンでは、SE RACの構築に必要なサーバやネットワーク機器、ソフトウェアのライセンスや構築費を込みにして、最低価格420万円からという価格が提示されています。この価格からもOracle Databaseが決して大規模だけに向けられた製品ではない、ということがおわかりいただけるでしょう。
Oracle Database Standard Edition」のライセンス体系と問い合わせ
http://www.oracle.co.jp/campaign/se_rac2007/index.html |
||||||||||
|
Oracle Databaseのライセンス Oracle Databaseを購入するときは、利用ユーザ数(Named User Plus)か、稼働させるサーバのプロセッサ数をカウントします。最近では1つのプロセッサに複数のコアを持つマルチコア・プロセッサが主流となっています。Oracle Databaseの3つのエディションのうち、Standard EditionとStandard Edition Oneについては、コアの数は特に意識する必要がありません。ただし、Enterprise Editionについては、コアの数を考慮しなくてはなりません。 コアの数を意識するのはプロセッサ数でライセンスを購入する場合で、プロセッサの種類によって定められた係数をコアの総数乗じる、というルールなのでやや複雑です。例えばIntel/AMDのプロセッサの場合には係数が0.5なので、デュアルコアのプロセッサを2つ搭載したサーバの場合は「4×0.5=2プロセッサ」となります。ところがクアッドコアのプロセッサを2つの場合は「8×0.5=4プロセッサ」となるわけです。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
1 2 3 次のページ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||