| ||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| システム運用のマネジメント改革が企業にもたらすもの | ||||||||||
システム運用マネジメント強化の取り組みが増える一方で、改革の志半ばで頓挫することや期待通りの結果が得られない状況に陥ることが少なくない。今回はシステム運用の業務の見直しやマネジメント改革の概要と共に、これら取り組みを阻害する企業内の「カベ」について説明する。 情報システムが企業活動に深く浸透している今日において、企業が事業の成果を着実に刈り取るためには、情報システムが安定して運用していることが大前提となる。 情報化サイクルの「企画」、「開発」、「運用」の3つの機能のうち、事業運営と表裏一体の関係にある「運用」は事業成果を受ける上で重要な要素となる。 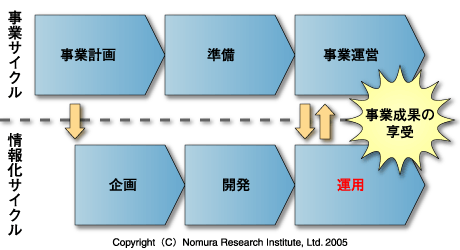 図1:事業サイクルと情報化サイクルの関連 | ||||||||||
| システム運用とはどんな業務? | ||||||||||
システム運用とは、情報システムが稼働中に発生する様々な業務の総称である。レガシーシステムの時代にメインフレームコンピュータを運用していた名残で、オペレーション業務と呼ばれることもまだ多い。しかし最近は、オンライン処理完結型の情報システムが増えていることや技術進歩によってオペレーション系の業務(例:マシン操作)の自動化が進んできているため、運用業務の大半は監視やインシデント対応、外部との情報の受け渡しになってきている。 これら運用業務を分類すると、日々の決められた作業を確実にこなす運行系、日々の業務の改善や情報システムの改修などの改善・支援系、業務運営や情報化運営のサイクルと密接に連携しつつ運用業務全体を管理・統制する管理系に大別される。  図2:システム運用業務の機能分類 | ||||||||||
| システム運用のマネジメント強化とは? | ||||||||||
システム運用が情報化運営サイクルの最下流に位置していること、情報システムの利用者から様々なインシデントを受け付けていることなどから、運用現場には情報化運営に関する全ての証跡が存在しているということができる。 システム運用のマネジメントの強化には、情報化運営の証跡を分析・活用し、システム運用の内部統制を強化することと、全社の情報化運営のレベルを上げることが考えられる。 | ||||||||||
| 運用部門の内部統制の強化 | ||||||||||
例えばインシデント管理業務において、運用部門がユーザからの問い合わせの応答率を継続的に管理し、前月や前年度実績などと比較しながら今後の応答率の改善に向けた業務改善を行うことがあげられる。 | ||||||||||
| 全社の情報化運営のレベルを上げる | ||||||||||
情報システムの稼働中に発生した障害やコスト状況を運用部門が管理を行い、これらの情報を運用部門から企画や開発部門にフィードバックを行い、さらにはプロジェクトの事後評価を行う局面で、インシデントの内容などを情報システムの品質という形で経営者にフィードバックすることがあげられる。 | ||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||

















