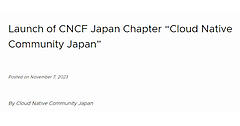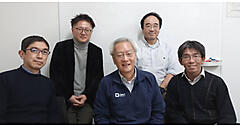「日本でオープンソースプロジェクトへのコントリビューションを増やすためには何が必要か?」これを考えるためのインタビューシリーズ第3弾は、日立製作所に所属するKeycloakのメンテナーであるエンジニアに話を聞いた。日本の伝統的な大企業でオープンソースにコミットする仕事を続けるようになった経緯や組織体制、そして課題などを掘り下げることがこの企画の意図である。コントリビュータが抱える課題や問題点、解決のためのヒントについてインタビューを通じて探り当てていきたい。今回インタビューに応じてくれたのは、株式会社日立製作所の乗松隆志氏だ。肩書きは「Hitachi OSPO / OSSソリューションセンタ 所属 シニアOSSスペシャリスト、Keycloakメンテナー」だ。
最初に簡単に自己紹介してください。
乗松:乗松隆志です。学生の時は数理系の研究でずっとMathematicaを使っていました。そこから新卒で日立製作所に入社して2025年で24年目になります。最初は通信機器の組込系の開発、そこからスマートメインテナンスというインフラ機器のメインテナンスのためのファームウェアの開発などを経て、2015年に社内でOSSソリューションセンタができるということで異動してきたという感じですね。今はKeycloakのメンテナーとして主に業務としてオープンソースソフトウェアへのコントリビューションとプロジェクトにまつわる仕事をしています。
日立はシステムインテグレーターとして顧客向けのシステム開発も行っていると思いますが、後方支援という感じでその現場でKeycloakを使ってもらう、そのためにオープンソースプロジェクトに参加するという感じですかね。
乗松:そうですね。私はOSSソリューションセンタでも他にあと一人ぐらいしかいないプロジェクトのメンテナーとしての仕事をメインにしている立場になります。そのため、プロジェクトの方向性とかレビューなどが中心になっています。後は啓蒙活動として日立のエンジニアがメンテナーなんだということを、KubeConなどを通じて外部に知ってもらうということを最近は特に心がけています。
ソフトウェア開発の仕事の進め方に関してですが、ソフトウェア開発についてシステムインテグレーターの社員として顧客のソフトウェア開発を行う仕事とオープンソースソフトウェアの開発はかなりスタイルが違うと思います。後方支援とは言ってもその2つを矛盾なく両立できているんですか?
乗松:一人のエンジニアがその両方を同時にやるということは余り起こらないとは思いますけど、日立スタイルでしか開発をしていないと外のことを知らないという状態になってしまうリスクがあると思いますね。なのでオープンソースのやり方でソフトウェア開発を体験するのは良いことだと思います。
一般的なケースとして、ITベンダーでもユーザー企業でもまず仕事で使っているツールがオープンソースで、それを使いこなしていくうちにコミュニティとも親しくなって、パッチを書くことからレビューをする側になって最終的にプロジェクトの中心的な存在になっていくというのが流れだと思いますが、乗松さんの場合は、組織、つまりOSSソリューションセンタが先にできてその中でKeycloakにコミットするというのが先行し、その後メンテナーという役割に当てはまったという感じですか?
乗松:OSSソリューションセンタの中村雄一さんという方がいまして、中村さんは最初から日立としてオープンソースをやる、そして単に使うだけではなくプロジェクトに積極的に入っていってその中で存在を認められるようにならないといけないという想いがあったと思います。それは明文化されていないかもしれませんが、もう一番最初からありました。なのでKeycloakを使う、パッチを書くだけに留まらないで、メンテナーとしてコミュニティに認められなければいけないということですね。
オープンソースで貢献をするというのは通常の企業であれば、知財に関わる話ですから、相当難しかったんじゃないかと思いますが、それはどうやってやったんですか?
乗松:具体的には説明できませんが、当初からオープンソースへの貢献は日立のビジネスのためになるんだということを役員にも説得できるように理論というか枠組みを組み立てたということだと思います。その枠組みの中にコードのコントリビューションやコミュニティへの参加も含まれていますので、私のメンテナーの仕事も業務としてやっていいということになっています。私もそれまで組込系の開発をやっていた経験から「社員として書いたコードは知財だし、それを無償で誰もが使えるように公開する」という発想には最初は違和感がありました。今は納得していますけど。
オープンソースへの貢献を認めてもらうことについて、つまり社内で書いたプルリクエストを認められるか? についてはNTTの水野さんと言う方が「オープンソースのOpenStackをUpstreamからForkして社内で開発をしていたらパッチが150件くらい積みあがっていて、それを知財と捉えると確かに知財なんだけど、このままではずっとメインテナンスしないといけない技術的負債になってしまう」ことから、全部をUpstreamにマージする方針に変えたということを言っていました。
●参考:日本でOSSのコントリビュータを増やすには何が必要か? 座談会形式で語り合う(前編)
業務としてやっているということですが、KPI的なものはあるんですか?
乗松:ありますね。プルリクエストの数やレビューの数、そして啓蒙という観点では海外のカンファレンスでどのくらい発表したのか? ということもKPIのひとつとして定義されています。
それは非常に幸せな環境だと思いますが、つまり業務としてオープンソースソフトウェアを使い、その改善をコードという形で提供して、技術的な方向性を考えたり、社外のコミュニティの参加者と交渉したりするという時間も認められているということですね。カンファレンスで喋るのも業務としてやっているのですか?
乗松:そうなります。啓蒙に関しては私がKeycloakのグループに入った直後からとあるカンファレンスがドイツであるから行ってこい、別のカンファレンスがイギリスであるからそこで喋ってこいみたいな業務命令がありまして、個人的には海外でそんなカンファレンスがあることも当時は知らなかったんですが、そういう機会を使って日立がオープンソースのソフトウェア開発に関わっていることをアピールをするというのが必須だったんです。
なぜかと言えば、ヨーロッパにおいて日立は原発とか鉄道などの重電や社会インフラの会社だと思われていて、ソフトウェア開発をやっているとは思われていなかったんです。でもそういうカンファレンスにはITベンダーだけではなく多くの事業会社が参加していて、そこから違う日立を知ってもらうということに繋がるんです。
別のコントリビュータのインタビューでは、仕事としてオープンソースに関わる中で2つのことが重要だと言っていました。それは業務時間に一定の割合でオープンソースに使って良い時間を作って欲しいということと、オープンソースへの貢献を業務の成果として認めて欲しいというものでした。その2つが実現できないと持続することが難しいというのがそのエンジニアの意見だったんですが、それに関しては乗松さんにとっては問題なさそうですね。
乗松:その2つ目のポイントについて、別の方のコメントになりますが、大事なのは評価を自分で行うのではなく他の人が行う仕組みを作らないとダメだということです。この仕組みは必ず作らないといけないということをその方は言っていまして、私も同意見ですね。
最初に役員にも説得できる形で「オープンソースへの貢献が自社のビジネスのためになる」ということを作ったことが非常に重要ですね。通常はユーザーからエキスパートになってオープンソースに関わるようになるというボトムアップが多いんですが、日立さんの場合は完全にトップダウンで実行されています。
乗松:実際のところ、OSSソリューションセンタも最初は今ほど評価方法が確立しておらず、自由にコミュニティへ参加して試行錯誤していたんですが、オープンソースへの貢献が日立のビジネスになるということは徹底されていたと思います。
乗松さんが新しく来た役員にそのことを説明して欲しいと言われたらできますか?
乗松:できると思いますけど、ちょっと準備は必要かもしれません(笑)。
乗松さんの仕事はかなり順調のように見えますが、何か困ったことはありませんか? 課題と言っても良いですが。
乗松:プロジェクトに関しては特に困ったことはないんですが、英語ですかね。特に技術的な内容で英語を使うことには難しさはないんですけど、カンファレンスとかでコミュニティの人と出会った時に世間話をするというのが非常に難しいと感じています。コミュニティの外の人たちとアイスブレークをする時に英語を使うのは未だに不得意ですね。
それは海外のカンファレンスでは「日本人あるある問題」ですね。テクニカルな会話はできても世間話になると途端に会話が止まってしまうっていう。日本人がKubeConで毎晩開かれるパーティに行かないのもそんなことがハードルだったりすると思います。乗松さんの後継者の育成については?
乗松:私が今やっているメンテナーの仕事は会社にも認められているのでゆくゆくは私の仕事を引き継ぐ人を育てる必要があるとは思いますが、今はOSSソリューションセンタも増員されているし人材も豊富なので、それほど心配はしていません。あと2~3年はこのままでも良いかなとは思いますが、将来的には必要になるでしょうね。
日立がトップダウンで「オープンソースに積極的に関与することで、ビジネスのプラスになる」という命題をクリアした上で継続的にKeycloakというデジタルIDに関するプロジェクトに参加していることは、日本の企業にとってのオープンソースプロジェクトに対する正しい姿として参考になるだろう。Keycloakについては中村雄一氏がThinkITに寄稿した以下の記事も参考にして欲しい。
またCloud Native Community JapanというCNCF公認の組織の一員として中村氏にインタビューを行った記事も参考になるだろう。
●参考:クラウドネイティブ啓蒙のためのジャパンチャプター結成の背景をインタビュー
興味深いのはこの時点(2023年11月)において中村氏は「個人ではなく組織として貢献する仕組みがまだできていない」と発言していることだろう。その当時はまだ社外に対して公開できるほどの枠組みが固まっていなかったと推測できる。
最後に日立の海外における鉄道事業に関する啓蒙のためのビデオを紹介しておこう。
●参考:The People of Hitachi: Leader in the Development of Europe's First Tribrid Train - Hitachi
これはPeople of Hitachiというシリーズの動画の一本だが、これのソフトウェア版、Keycloakに貢献することの意義を中村雄一氏が啓蒙する動画もぜひ期待したい。