| ||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||
| SQL Server 2005のインストール 〜 クラスタノード | ||||||||||||||
インスタンスの設定までを行うと、次はデータベースクライアントの接続先となる仮想サーバ名の入力画面が表示されますので、今回は「MSCS-Virtual」と設定します。 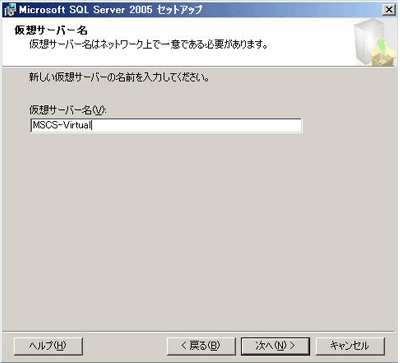 図6:仮想サーバ名の設定画面 仮想サーバ名を決めた後は、仮想サーバが使用するネットワークとIPアドレスの設定を行います。今回の環境では表2のようにします。
表2:仮想サーバの設定内容 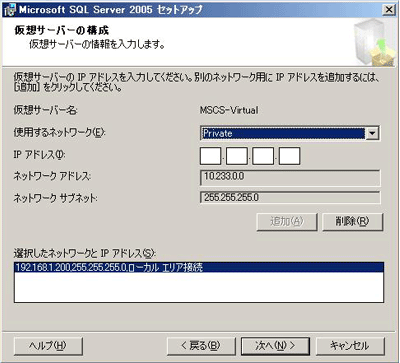 図7:仮想サーバの構成画面 仮想化サーバの設定が終わると、「クラスタグループ」の選択画面が表示されます。ここで選択したクラスタグループに対して、SQL Server 2005の仮想サーバが利用するリソースのインストールが行われます。 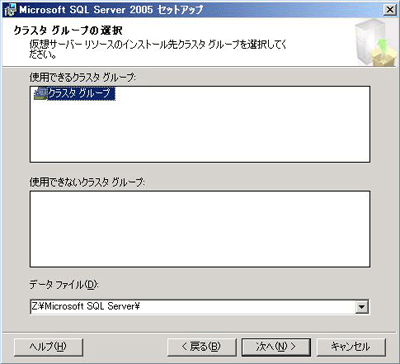 図8:インストール先クラスタグループの選択画面 クラスタノードの構成画面では、仮想サーバをインストールする先のノードを指定します(今回はそのまま先に進みます)。 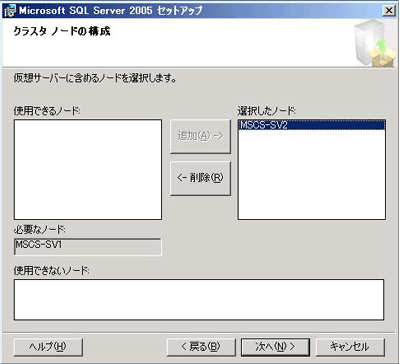 図9:仮想サーバのインストール先クラスタノードの選択 SQL Server 2005のインストールに使用する「リモートアカウント情報」の登録画面が表示されるので、MSCSを構成しているすべてのクラスタノードに対して、管理者権限を持っているアカウントとパスワードを入力します。通常はActive Directoryドメインの管理者アカウントを入力します。 次にSQL Server 2005のサービスアカウントの設定画面が表示されます。SQL Server 2005の仮想サーバで利用するアカウントは、ドメインアカウントを設定する必要があるため、アカウント情報はすべてドメインの管理者アカウントを設定します。また、「サービスアカウントごとにカスタマイズする」にチェックを入れることで、登録するサービスごとにアカウントとパスワードを設定することも可能です。 今回は「アカウントごとのカスタマイズ」を行いません。 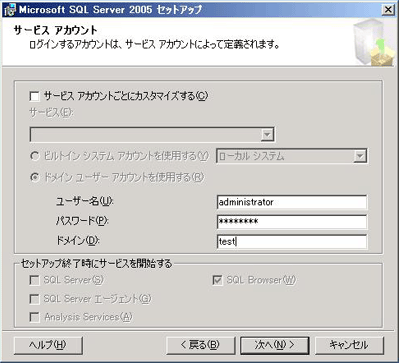 図10:インストール時のアカウント入力画面 「クラスタ化されるサービスのドメイングループ」で、クラスタ化されるサービスの開始アカウントをドメインのグループへ登録するメッセージが表示されます。ここでは、すべての項目に「TEST\Domain Admins」を指定して先に進みます。 「認証モード」の設定画面では、「混合モード」を選択し、saのパスワードを設定します。 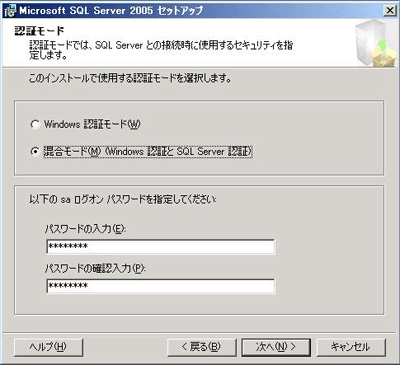 図11:ドメイングループへのサービスアカウントの登録 照合順序の設定では、今回はとくに設定をせずに「サービスアカウントごとにカスタマイズする」のチェックをはずした状態にします。「エラーと使用状況レポートの設定」についても、設定を行わずに先に進みます。 ここまで設定を終えると「インストールの準備完了」画面が表示されるので、インストールするSQL Server 2005の機能およびコンポーネントを確認してインストールを行います。 「Microsoft SQL Serverセットアップの完了」という画面が表示されれば、インストールは完了です。これでSQL Server 2005のフェイルオーバークラスタ構成の構築は無事に終了になります。 | ||||||||||||||
| SQL Server Service確認方法 | ||||||||||||||
SQL Server 2005のインストールが終了したら、サービス状況を確認しましょう。 手順としては、「マイコンピュータ」を右クリックして、プルダウンメニューから「管理」を選択し、「コンピュータの管理」を開きます。右側にある「サービスとアプリケーション」を開いて、「MS SQL Severサービス」が正常に登録されており、正常にサービスが稼動しているか確認をします。 「MSCS-SV1」および「MSCS-SV2」の双方で正常にサービスが稼動していれば、インストールは成功です。クラスタグループにインストールを行ったので「MSCS-SV2」側にも自動的にもサービスが登録されています。 今回は、構築したフェイルオーバークラスタリング環境にSQL Serer 2005を導入する方法と注意点を紹介しました。次回は、構築した環境を利用して、実際にフェイルオーバーの動作確認をしていきます。 | ||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||



















