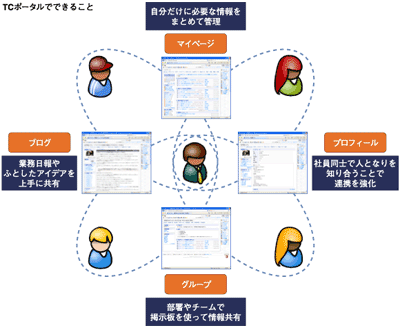|
||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||||
| 社内のナレッジを共有せよ | ||||||||||||
|
社内の情報や知識(ナレッジ)を共有することは、多くの企業にとって長年の課題であるといえます。特に企業が大きくなり、組織が縦割りになればなるほど、部門や事業部を超えた情報共有が困難になります。 そういった状況では、グループウェアなどの仕事の延長上にあるツールを使うだけでは、仕事以外の話を含めた全社横断のコミュニケーションやナレッジの共有は難しいかもしれません。その課題を解決する可能性を秘めているのが「社内SNS」です。 SNSとはソーシャルネットワークサービスの略で、最近ではmixiが非常に有名です。
mixi
http://mixi.jp/ mixiは登録制の閉じた世界でのコミュニケーションツールで、プロフィールの登録や日記の投稿やコメント、コミュニティなどによって、人と人のつながりを構築・支援することを目的としたサービスです。 そして今、このSNSの仕組みを社内に導入することで、社内の情報共有に効果を発揮できるのではないかと期待されはじめています。 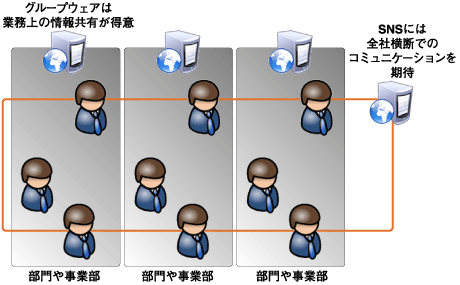 図1:社内SNSへの期待 そこで本連載では、筆者が所属するTISに社内SNSを導入した実践経験を基に、その可能性を探っていきます。 第1回の今回は、社内の情報共有の手段として、なぜSNSを採用したのか、SNS導入までの経緯とその目的や狙いについて説明します。第2回以降では、一般的なSNSの機能とは異なる社内SNSに求められる機能や、運営上のノウハウについて紹介していきます。 |
||||||||||||
| 社内SNSの事例紹介 | ||||||||||||
|
まずは、本連載で題材として扱うTISで導入した社内SNSの事例を紹介します。今回導入したSNSは、一般的に「社内SNS」と呼ばれるもので、社員だけで利用し合うことを想定したものです。正式名称は「TIS Communication Portal」ですが、社内では通称「TCポータル」と呼ばれています。 社内SNSにもかかわらず、「ポータル」という言葉を付けたのは、社内SNSの機能に加えて、社内の他システムへの入り口としてのポータル機能を持たせているためです。この理由については、後ほど解説します。 この社内SNSは2005年12月から運用を開始し、現時点(2007年3月末)で1年4ヶ月の運用実績があります。社員数約2,800名に対して、約700名の登録者があり、社内の4分の1程度の社員が登録しています。 |
||||||||||||
|
1 2 3 次のページ |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||