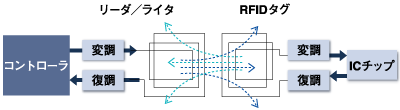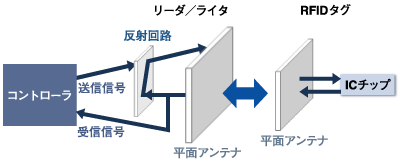|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFIDタグの動作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
このように、RFIDは既存のバーコードシステムに比べて機能面での汎用性が高い分、導入には細心の注意が必要である。特に、RFIDタグで利用される無線周波数の特質や、さらに製品ごとに異なる機能の理解なくしてRFIDシステム導入の成功はありえない。そこで以降では無線技術に着目し、RFIDタグの動作原理について解説する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッシブタイプとアクティブタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RFIDタグは、その通信方式からパッシブタイプとアクティブタイプの2つに大別される。パッシブタイプとは、RFIDタグを起動させるためのエネルギーの供給が外部から行われるものであり、もう一方のアクティブタイプとはRFIDタグ内部にエネルギー供給源であるバッテリを搭載したものである。 従って一般的には、パッシブタイプよりもアクティブタイプの方が電波の通信距離が長くなる。ただし、アクティブタイプはバッテリを搭載する分、高コストとなるだけでなく、数年のサイクルで廃棄もしくはバッテリの交換が必要になる。もう一方のパッシブタイプは、低コスト化と長寿命化を実現できるため、次世代バーコードとしての期待が高い(表1)。
表1:パッシブタイプとアクティブタイプ 出所:野村総合研究所 その他にも、外部の読み取り機(リーダ/ライタ)から電波を受けた後、タグ内部に搭載したバッテリを用いて電波を発信するセミパッシブタイプがある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パッシブタイプのRFIDタグは外部アンテナと送受信を行うアンテナとICチップから構成される。ICチップを駆動させるための通信方式は、電磁結合方式、電磁誘導方式、電波方式の3方式が代表的であり、利用する周波数によって使い分けられている。
表2:パッシブタイプの通信方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RFIDタグは電波を用いて情報の伝達を行うため、周波数の特性と関連法規制についての知識が必要になる。RFIDタグで利用される周波数は大きく4つに分類され、周波数ならではの特性のみならず、標準規格もそれぞれ異なる(表3)。
表3:周波数の特徴、RFIDタグ、関連規格 出所:野村総合研究所
※注:
通信距離は、システム構成や製品ごとに異なるため表記は参考値
135KHz以下、および13.56MHz帯の周波数を使うRFIDは、水への透過性(水分を有するモノに貼り付けしても認識が可能であること)やアンテナの指向性の広さなどの特徴がある。一方、UHF帯やマイクロ波帯は前2者に比べると指向性に優れる一方、水の透過性が悪いなどの課題がある。 またRFIDタグのまわりに金属物質がある、あるいはRFIDタグを利用する対象物そのものが金属物質の場合、性能が著しく劣化してしまう。最近では、金属物質に対応したRFIDタグが提供されているが、交信距離は通常のRFIDタグより劣るほか、コストも割高となってしまう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前のページ 1 2 3 4 次のページ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||