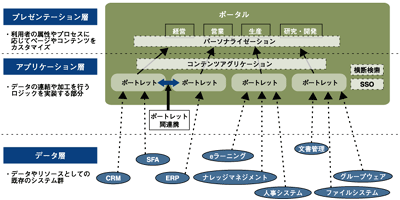| ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 | ||||||||||||
| ポータル機能のまとめ | ||||||||||||
今回解説したポータルの機能について全体感をまとめてみると図5のようになる。 みずほ情報総研では、ポータルの機能がそれぞれどのような役割を担っているか、他のシステムとの関連を含めてデータ層、アプリケーション層、プレゼンテーション層の3つの階層に分けてポータルの全体感を捉えている。 つまり企業における「情報のありか=既存のシステム群」をデータ層と見立てれば、データを取得し連結や加工処理を行うポートレットがアプリケーション層となる。そしてパーソナライゼーションは、利用者とのインターフェースとなるプレゼンテーション層の機能と位置づけることができるだろう。 このように定義することで、よりポータルの全体感がつかめるだろう。 | ||||||||||||
| 機能を最大限に引き出し、効果的なポータルを構築するために | ||||||||||||
ポータルが持つ機能は非常に魅力的で技術検証や試行程度であれば、比較的短期間に導入することができる。ただし過去のポータル導入プロジェクトの取り組み状況を見てみると、これらの機能が十分に活用されている事例はあまり多くない。 例えばEIPツールが提供する標準のポートレットを利用して、グループウェアやファイルシステムのユーザインターフェースをWebブラウザに代替しただけのものや、検索エンジンやシングルサインオンなどの単機能を提供するだけにとどまっている場合がほとんどである。 あるいは、やみくもに社内アプリケーションとの連携やパーソナライゼーション機能を多用した結果、試行段階から本格導入を目指す段階で期待するパフォーマンスが得られず、全社に展開されないままになっているプロジェクトもある。 これらはビジネスとITの視点からの検討が、事前に十分行われていなかったことが原因であると考える。つまり業務上の最終目的があいまいなままで、ポータルを構築することが最優先の目的となってしまい、明確な指標もなく技術検証や試行をはじめてしまったということだ。 このようにして開始したプロジェクトは、ポートレットにどのような機能を持たせるべきか、利用者にどのようなシーンで情報内容を提供すればよいのか、アプリケーションやプレゼンテーション層のどの部分で実装すればよいのかなどが見定められないまま開発フェーズに入ってしまう。結果として構築されたポータルは、業務上での使い勝手が悪く、利用部門に使われないものになってしまうのである。 成功裡に導入され、ポータルが企業インフラとして不可欠なものとなっている企業では、明確な目的の設定と企画段階において利用者とシステム両方の視点で現状分析が十分に行われていることが多い。 ポータル導入を成功に導くためには、企画段階でどのような事項について検討を行えばよいのだろうか。次回は導入にあたって押さえておくべきポイントについて具体的に解説していこう。 | ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||