| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の評価に使用したのは、「DBT-1」および「MaxDB」である。 DBT-1はTPC-Wの仕様を一部取り込んだベンチマークツールで、Web3層構造のうちクライアントおよびアプリケーションサーバを提供する。 DBT-1のインタラクション(トランザクション)は14種の規格中12種類が実装されている。インタラクションの分布は規格通り実装されているが、TPC-Wを実装していない規格も多く、OSDLではDBT-1の結果をTPC-Wの結果として言い換えないよう、注意を促している。 OSDL Database Test 1(DBT-1) http://www.osdl.org/lab_activities/kernel_testing/osdl_database_test_suite/osdl_dbt-1/ MaxDBは独SAP AG社がERP用RDBMSとして利用していたAdabas Dを、2000年よりSAP DBの名称でオープンソースとして公開していたもの。現在は、MySQL AB社とクロスライセンシングを行い、MySQL AB社よりMaxDBの名称で公開されている。 MySQLのWebサイト http://www.mysql.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSDL DBT-1の構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここでは、使用したツールDBT-1がどのようなものであるかについて述べる。 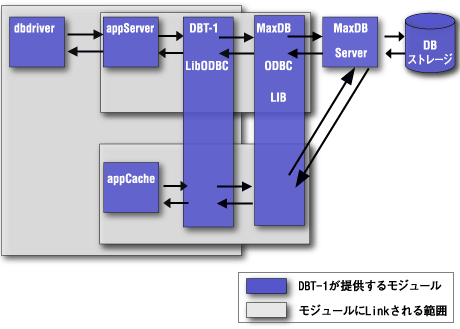 図1:DBT-1のプロセス構成 仮想ユーザは、dbdriver内のスレッドで実装され、指定した時間内で14のインタラクションを繰り返す。また、起動シェルでは各プログラムをリモートで起動するようになっており、より本番に近い環境での評価を可能とする。 測定の開始は、全ユーザが接続している間を対象とし、評価結果は毎秒のトランザクション数(BT/秒)と各処理の平均時間が得られるほか、システムリソース情報(sar)およびDBの状況も収集する(表1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1:DBT-1(MaxDB)ログ情報一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2:主要パラメータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















