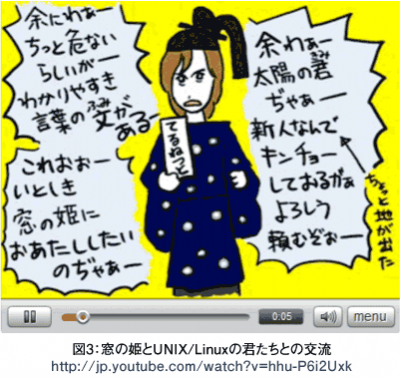案外めんどかったのがTelnet
案外めんどかったのがTelnet
次にtelnetサーバです。クライアントと込みで、同じくWindowsの機能として有効化します。
Windowsがサーバですので、UNIX系のほうは、今度はほかのクライアントさまに御登場願いましょう。
Telnetのクライアントさまはピカピカの新人君、OpenSolaris 2008.5(http://www.thinkit.co.jp/article/82/1/)。最近のLinux系ではtelnetが標準で使えなくなっているものが多い中、こちらは当たり前のようにtelnetが打ち出せます。
と思ったらつれないVistaから、ピシャンとアクセス拒否です。ガッ!?
大丈夫、ちゃんとマイクロソフトの「Telnetサーバーへのアクセスを許可する(http://www.microsoft.com/japan/technet/windowsserver/2008/library/22b0b471-1fa8-419d-ba60-b0afa1455429.mspx?mfr=true)」という文書にありました。
作業は「管理ツール」「ローカルユーザーとグループ」で行います。「Telnetサーバー」を有効にしたことで、「TelnetClients」というグループがすでにできています。これに、Vistaのユーザ名を追加してやればいいのです。あとはOpenSolarisから、Vistaのユーザ名とパスワードでログオン。
LinuxとはSUAのSSHで
ではLinuxはと言うと、SSHを使うのが主流です。
Windowsの機能にはSSHはありませんが、「第3回:SUAのコミュニティに潜入!(http://www.thinkit.co.jp/article/86/3/)」で怒とうのインストールを敢行したInterix用パッケージのOpenSSHがあります。
まず、クライアントを試してみましょう。SUAのシェルから、ほかのサーバさまにsshコマンドでアクセスしてみます。ハイ、全く問題なし。
さてSUAはSSHサーバになれるのでしょうか。今度はLinuxのクライアントさま御登場です。
今度はさらに執筆時点(2008年6月16日)でデビュー前のOpenSUSE11 RC1君です。数日後の2008年6月19日に正式版がリリース(http://news.opensuse.org/2008/06/19/announcing-opensuse-110-gm/)されました。
OpenSUSEからSUAをsshで呼び出してみます。応答がありません。
あッ。気がつきました、ファイアウォールです。いつもなら「怪しき者がお目通りを願っておりますが追い払いますか」というウィンドウが出て「構いませぬ、通しやれ」と申してつかわせばいいのですが、SSHはWindowsの直接の機能ではないのでふさがったままなのです。
ポートを開けるのはWindowsからGUIでできます。「コントロールパネル」で「セキュリティ」の設定から、「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」を選びます。
「SSH」というプログラムは想定されていないので、「ポートの追加」で22番を直接指定して開いてやります。
つながりました。おまけにOpenSUSEのKDE4では、FISH(FTP over SSH)というプロトコルで、KDEのファイルブラウザで直接Vistaのフォルダを操作できるのです。
ユーザはそれが魚か野菜かを気にする必要はありません。グラフィカルな「ネットワークプレースの追加」ウィザードで、プロトコルに「SSH」を設定するだけ。共有フォルダ名は、SUA形式(/dev/fs/C/Users/nonikoのような)を指定します。
さて本連載「SUAって何だ!」4週間お楽しみいただけましたでしょうか。「UNIX系の勉強をしたいけど、別途導入できない」事情がある方、Vista Ultimateをお持ちなら使って見られればよいのデハ。むしろ何から何まで揃っちゃってる昨今のPC-UNIXより、冒険できて面白いかも知れませんョ。
- この記事のキーワード