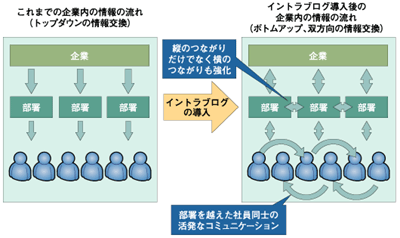| ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||||
| What(課題):イントラブログで何を行うのか? | ||||||||||||
次のポイントは「What(課題):イントラブログで何を行うのか?」ですが、このポイントははじめに決めたイントラブログ導入の目的によってある程度決まってきます。 まず、「社内コミュニケーション力の強化」を目的としてイントラブログを導入する場合ですが、この場合には喫煙所や飲みュニケーションのような、社員間の自由なコミュニケーションの場としてイントラブログを導入します。 特に内容に制限を設けず、社員1人1人が自分のブログで普段の業務で感じたこと、業界の気になるニュース、仕事に対する考え方など積極的な情報発信を行うことで、活発なコミュニケーションが生まれます。 次に「個人ナレッジの蓄積」を目的としてイントラブログを導入する場合ですが、この場合には作業メモや業務日報、研修日報などの情報を共有する場としてイントラブログを導入します。 一般的に日報はフォーマットが決まっていて堅苦しいものですが、イントラブログの場合はフリーフォーマットですので、個人の意見や考え方がストレートに発信されます。 その結果、個人が持つノウハウやナレッジが蓄積されるようになりますので、優れたナレッジマネジメント効果を生み出すことができます。 最後に「業務効率化、業務改善」を目的としてイントラブログを導入する場合ですが、この場合には業務の効率化や改善を目指し、すでに導入されているツールのかわりとしてイントラブログを導入します。 例えば、メーリングリストのかわりとしてイントラブログを導入することで、煩雑で大量のメール処理から開放され、効率良く情報を管理できるようになります。あるいは掲示板のかわりとしてイントラブログを導入することで、限られたメンバー間での情報共有やプロジェクト管理などにも利用することができます。 もちろん、上記の3点すべてを目的としてイントラブログを導入することは可能ですが、目的を多くしてしまうと敷居が高くなってしまい、イントラブログのよさである手軽さ、簡易さが失われてしまうことになってしまいがちです。よって、導入にあたってはなるべくシンプルに目的を設定することをお勧めします。 | ||||||||||||
| Where(対象者):イントラブログを実際に使う人は誰なのか? | ||||||||||||
次のポイントは「Where(対象者):イントラブログを実際に使う人は誰なのか?」です。 一般的に会社の情報発信は上司から部下というトップダウンによって行われますが、イントラブログは社員1人1人に積極的な情報発信を促し、コミュニケーションを活性化させるものです。よって部下から上司というボトムアップを行うためのアプリケーションであるということを強く意識する必要があります。 実際にイントラブログを導入しても、社長や役職者しかブログを書かないということであれば、そのメリットはほとんど皆無となります。 また、社長や役職者がアルバイトや一般社員の意見やコメントを無視してしまったり、軽く捉えてしまうのであれば、イントラブログを導入すること自体が無意味なものになってしまいます。 社員1人1人による積極的な情報発信が将来的な会社の財産になると考え、社長であろうがアルバイトであろうが、ベテランであろうが、入社初日であろうが、イントラブログ上では同じ立場で情報発信できること、つまり、イントラブログは社員のためのアプリケーションであることを会社全体として強く意識することが非常に重要なポイントです。 | ||||||||||||
| How(実現手段):どのようにしてイントラブログを普及させるか? | ||||||||||||
次のポイントは「How(実現手段):どのようにしてイントラブログを普及させるか?」です。 イントラブログは社員のためのアプリケーションですが、イントラブログを導入し、社員1人1人による積極的な情報発信を行うように強制したとしても、社員からの積極的な情報発信はあまり見込めません。 これはやはり、自分の意見を積極的に発信すること、ボトムアップすることに対しての抵抗感や、単純に作業が増えてしまうことへの面倒くささなどが原因です。この抵抗感や面倒くささを払拭するためには、率先して情報発信を行ういわゆる「サクラ」のような社員が必要です。 このサクラのような社員は、もちろん業務の一環として会社の指示で任命しても良いのですが、できれば普段からプライベートでブログを書いている社員や、社員の中でも影響力が大きい社員に、率先して情報発信をしてもらうように協力してもらうことが重要です。 このような、他の社員に影響力を持つ人のことを「インフルエンサー」と呼びます。社内のインフルエンサーが積極的に情報を発信することで、イントラブログによる情報発信が一般化し、段々と情報発信する社員が増えていきます。 | ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||