| ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||
| データベースの可用性を実現する技術、主流は「クラスタリング」 | ||||||||||||
データベースの高可用性を実現する技術として現在主流となっているのは、クラスタリングだ。クラスタリングとは、複数のコンピュータを接続してひとつのシステムを構成し、ユーザの側からは1台のコンピュータとして見えるようにする一種の仮想化技術である。 ハードウェアとしてのコンピュータ(データベース)は複数存在するが、それをソフトウェア上で1台として見せることでシンプルな操作・管理が容易になる。また必要に応じてデータベースを増設できるため、システム構築後でもパフォーマンスの向上や容量アップを行えるメリットがある。あらかじめ負荷を分散しておくことで、過負荷によるシステムダウンを回避するといった、予防的な利点も備えている。 クラスタリングの他には、フォールト・トレラントサーバを用いた、ハードウェアレベルでの二重化などの方法もあるが、現在主流となっているのはこのクラスタリングだ。 もちろん主要な商用データベース製品も、クラスタリングには大きな力を注いでいる。まずOracleは、Oracle 9iからOracle RAC(Real Application Clusters)というクラスタ・アーキテクチャを導入、一方Microsoft SQL ServerもSQL Server 2000からシェアード・ナッシング型のクラスタリング技術を導入している。DB2 UDBも、V8.1で採り入れた多次元クラスタリングやLinux向けのクラスタリング機能の積極的な導入といった取り組みを行ってきた。 各社とも技術的な面で細かな違いはあるものの、クラスタリングのメリットとしては、下記のような主に障害時のシステム停止リスク回避と導入コストの抑制効果を挙げている。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
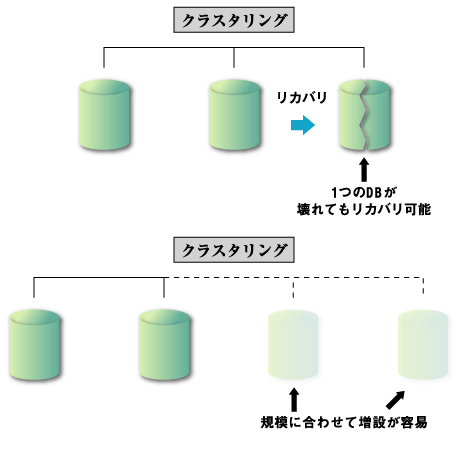 図2:クラスタリングのメリット | ||||||||||||
| エンタープライズ用途に意欲的なOSS DB | ||||||||||||
では、OSS(オープンソースソフトウェア)データベースの可用性は、どういった状況だろうか。 先に挙げた商用データベースは、Microsoft SQL Serverを除いてLinuxとのクラスタリング環境を以前から提供している。Oracleは全製品をLinuxに対応させることをうたい、最新バージョンのOracle RAC 10gにおいても、積極的なLinuxへの取り組みを行っている。また、IBM DB2 UDBも「DB2 for Linux」のスローガンのもとで、コストパフォーマンスに優れたデータベースによるe-businessの成功を訴求している。 「でも、それはあくまで商用データベースの側からの取り組みだし、それもLinuxに限ってのことではないの?」 ご指摘の通りだ。そこで、MySQLとPostgreSQLの2大OSSデータベースに関して現状を見てみよう。商用DB製品に必ずクラスタリング用ツールが存在するのと同様に、当たり前だがOSSデータベースにもちゃんとクラスタリング用ツールが用意されている。 PostgreSQLでは、共有分散型クラスタ構築用に「LifeKeeper」、負荷分散型クラスタを構成する「QueryMaster」などがあり、いずれも商用製品として販売されている。またレプリケーション機能をPostgreSQLに追加する「dbmirror」は、PostgreSQLのコントリビューションとしてアプリケーションに付属している。 一方のMySQLは、2004年の4月に開発主体であるMySQL AB社(スウェーデン)から、新しいOSSデータベース用クラスタリング技術「MySQL Cluster」が発表された。これはMySQLデータベース本体とクラスタリング・アーキテクチャを組み合わせて99.999%の可用性を実現するというもので、同社によれば、「初の低価格なエンタープライズ級のDBクラスタリングソフトウェア」だという。 この高い可用性に加え、高速のレスポンスタイム、クラスタごとにフォールト・トレラント化されたデータベースなど、エンタープライズ・データベースとして必要な機能を搭載。また専用のハードウェアや共有ディスクストレージが不要なため、コスト的にも優れているという。かねてからMySQLの処理速度の速さにはビジネスユーザから定評があったが、こうした機能を追加したという事実が、今後エンタープライズ系分野に打って出ようという意欲を感じさせる。 | ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||

















