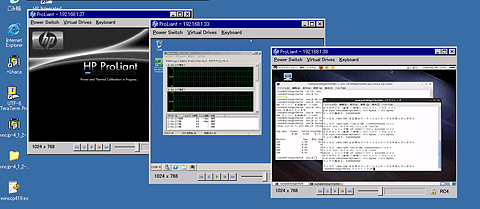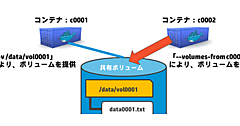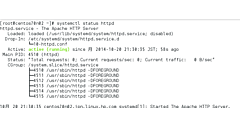仮想化やクラウド・コンピューティングの発達によって、コンピュータ・システムはますます複雑になっています。仮想化技術やクラウド・コンピューティングを導入すると、エンドユーザーの立場では、非常に使い勝手がよく、電力消費や物理サーバーの台数が抑えられるというメリットがあります。この一方、運用管理を行う立場では、個々の物理サーバーやゲストOSがどのような状態なのかを正確に把握しておく必要が生じます。
システムの管理者は、サーバーの状態やアプリケーションの稼働状況を把握するために、さまざまなツールを駆使します。実績が豊富な有償のツールもあれば、無償で提供されている優秀なツール、そうでないツールも存在します。このため、自社のシステムに合った実績のある手法を見極める必要があります。
本連載では、物理サーバー・レベルでの管理の基本を紹介しつつ、特に近年クラウド・コンピューティングに採用が検討されている、Red Hat Enterprise Linux 6とFreeBSDに適用可能なOSS(オープンソース・ソフトウエア)を使った運用監視と、ベンダーが提供する無料の監視ソフトウエアによる運用管理の手法を紹介します。
サーバー管理手法
ITシステムの管理者は、物理的なサーバーやストレージの状態を把握するために、サーバー・ルームに足を運びます。サーバーの物理的な状態を確認するためには、ハードウエアが搭載しているLEDの色、点滅、点灯状態、警告音の有無、などを確認する必要があります。
サーバーやストレージの異常を、人間の目視によって確認することは、非常に重要なことです。しかし、目視だけでは分からない異常も、数多く潜んでいます。目視だけでは分からない異常は、サーバーにログインして確認します。管理対象がLinuxやFreeBSDなどのサーバーである場合は、端末エミュレータを使ってログイン・プロンプトを出し、コマンドを入力することで管理できます。
一般的に、ハードウエアの状態は、目視で確認する場合が多くみられます。しかし、サーバー・ルームが遠隔地にある場合は、管理者の移動のための交通費削減という観点から、遠隔からの管理が行われます。遠隔からの管理手法を理解しておけば、管理者は地理的な制約から解放されるため、非常に効率的です。
ハードウエアが遠隔地にある場合は、クライアントから管理対象のサーバーに管理専用ネットワーク経由でログインすることで、管理を行います。管理対象のサーバーにOSがインストールされている場合は、telnet、ssh、VNCなどを利用して遠隔操作を行います。一方、OSがインストールされていない場合でも、遠隔地からサーバーの電源ON/OFFやBIOS設定、RAIDコントローラの設定、POST画面のコンソール表示とキーボード操作を行えるようにしておくことが重要です。
一般には、仮想電源ボタンや仮想コンソールなどの豊富なサーバー管理インタフェースが用意されています。これにより、管理者の管理工数を大幅に低減できます。これらは、規模の大小に関係なく、サーバーの運用管理には必須ともいえるコンポーネントとなっています。
例えば、HP ProLiantサーバーに搭載されている管理チップであるiLO3による仮想電源ボタン、仮想コンソール、仮想メディアを駆使することで、OSのインストールの前段階のハードウエア管理で威力を発揮します。最新のiLO3仮想コンソールでは、複数の管理コンソールを複数開き、ウインドウを拡大・縮小できる機能が備わっています。これにより、複数のLinux、FreeBSD、Windowsなどを1台のクライアントPCの1画面上で、コクピットのように管理できます。
以下の図では、遠隔地にある、OSが入っていないサーバーと、それぞれRed Hat Enterprise Linux 6とWindows Server 2008 R2がインストールされている、合計3台のサーバーの画面を、1つのクライアントPCの画面上で縮小表示させ、操作を行っている様子です。
| 図1: 最新のx86サーバー向け仮想コンソールでは、遠隔地にある複数のサーバー画面を縮小表示し、コクピットのように操作が可能。クライアントPC側はWebブラウザで操作ができる(クリックで拡大) |
従来であれば、ディスプレイ切り替え機を用いて1台ずつサーバーの画面を出力して切り換えて確認していました。これが、上図のようなサーバー搭載の管理チップの機能を使うことで、サーバーの死活状態やOSの状況などをクライアントPCの1画面に集約して確認できるようになりました。管理効率を大幅に向上させることができます。
Linux、FreeBSDサーバーのハードウエア情報の取得とOS管理
LinuxやFreeBSDなどのオープンソース・ソフトウエアを同梱(どうこん)したサーバーの稼働状況を把握する一般的な方法は、OS付属のシステム管理用コマンドを駆使して情報を収集するというものです。サーバーのコンポーネントであるCPU、メモリー、RAIDコントローラ、RAIDコントローラ配下のディスク、NICの状態を管理します。
最新のRed Hat Enterprise Linux 6やFreeBSD 8.1では、コマンド・ラインとGUIによる、ハードウエア・コンポーネントの管理、監視が行える、便利なツールが用意されています。以下では、世界的に圧倒的なシェアを誇る米Red Hatの最新OS、Red Hat Enterprise Linux 6と、Web系システムで採用が見られるFreeBSDに関する管理手法を紹介します。