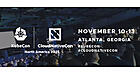紙の出版と電子出版の根本的な違い
電子出版は新しいジャンルではない。しかしながら、昨年2010年が「元年」となったことは明らかだ。米国を考えれば、もっと前からリリースされていたAmazon Kindleの存在が大きいが、日本国内はそうした動きを横にらみしつつも、2010年に発売されたiPadによってその可能性が一気に注目されたことが大きい。
注目された理由の1つは、アプリ配信を行うApp Storeと同じように、書籍流通をApple配下に構築した「iBooksストア」の存在がある。ただ、残念ながらまだ日本のコンテンツの流通には至っておらず、出版社や著者がApp Store上に書籍アプリとして独自にリリースしているのが現状だ。
日本でiBooksストアが広まらない理由として考えられるのは、そういった新しい流通形態が勢いを増すことで、これまでの枠組みが崩れてしまうではないかという、出版業界全体の不安があるのではないだろうか。かくして、Kindleの日本語版、ソニーやシャープのリーダデバイス等含めて、電子書籍自体は盛り上がったものの、肝心のコンテンツについては今ひとつ先に進めなかった感がある。
そうして電子書籍の市場も混沌としてきて、今後どうなるのかということも気になるようになってしまった。この問題を解決するには、まず現状を理解して、どんな立場の人たちが関わっているかを考えれば良い。書籍出版を大きく分類すると、コンテンツ所有者あるいは制作者としての「筆者」、コンテンツを配布する「出版社」、そして「流通」となる。
現在は出版社に大きな存在感があるが、それはなぜか?大きな理由は筆者と出版社が排他的な契約を一般には結ぶからだ。従って、1つのコンテンツは1つの出版社のある意味所有物となる。そして、出版社によって企画から制作、配布が行われないものは「自費出版」という別ジャンルと化してしまう。また他にも、取次と出版社、書店と取次のように、事実上排他的な契約でビジネスをしている「サークル」がある。これらを考えると、書籍出版のための枠組みはそう簡単には覆せない。
しかしながら、電子出版に期待されているのは少なくともそうしたやり方のショートカットができそうな点である。AmazonやiBooksも含めて、これまでの「流通」は少なくとも抜きになるかもしれないという期待がある。かくして、有力な著者はもはや出版社の助けすらもいらないと、独自にビジネスを起こすまでに至っている。電子出版は21世紀の初頭に業界が新しく形成されたというのが、ともかく大きな違いの根源と言える。
| 図1:iPad発売当初から存在したアプリケーション版の「不思議の国のアリス」。例えば、見えている時計が動くなどソフトウエアならではの仕掛けもある(クリックで拡大) | 図2:iBooksで無償配布されている「Winnie-the-Pooh」。iBooksのアプリケーションでは紙の本のようにめくって見るという感触の動作である(クリックで拡大) |
コンテンツ市場の「主役」は誰か
iPadをはじめ、電子書籍を閲覧するためのいろいろなデバイスが出てくるのは楽しみだが、少なくともこれらがコンテンツ市場の主役でないのは確かだ。コンテンツ流通という意味では、iPadでさえも脇役なのである。現在業界で主権を握っている出版社も当然主役ではない。電子出版分野で最初に成功したと言える、Kindleの伸展の理由をよく考えてみよう。AmazonはKindleを売って儲けようとしているのではない。コンテンツを売ることを強く意識している。だからMacやiOSでも使えるようなソフト版も出してるわけだ。かくして、Amazonの大きな売り上げの割合をすでに電子コンテンツが占めているという状況になった。コンテンツが主役だという考え方をAmazon流に展開したのである。つまり、コンテンツ市場の主役は「筆者」であることは間違いない。
いずれにしても、コンテンツが出てこないと出版は成り立たない。そのコンテンツはどう作ればいいのかということに注目が集まるのは当然だ。業界標準とも言えるEPUBが1つの結論であることは言うまでもないが、現実的にはいろいろある。PDF、HTML、さらには独自アプリケーションだっていい。筆者はどんなフォーマットでも書ければ良く、読者は読めればいい。フォーマットは舞台裏の話であり出版社的な話題なのだ。
日本ではiBooksが開始されないので、結局それなら「App Storeにアプリとして掲載すれば、取りあえずは売り始められる」という結論のものと、実験的あるいは筆者の熱意などで一部のコンテンツがアプリとして出始める状況になり、混沌を深めている印象もあるかもしれない。
日本でフォーマットを決めようといった動きもあるのだが、出版社的にはある意味なんでもいいという意図がある。規格に従えば、後から別のプラットフォームに移行しやすいというメリットもあるが、フォーマットそのものがキモとはあまり考えられていない。コンテンツのキモは中身だ。結局のところ、流れに合わせるしかないし、それがどう決まっていても合わせる作業が発生するのはいっしょだからだ。
しかしながら、XMLの利用は本格的になるというのはいろいろな切り口からは明らかだろう。従来はともかく紙への印刷という最終形が決まっているため、DTPや印刷という仕組みに集約されていた。今後は「なんでもあり」なら、自由度の高いことが優先されるということだ。