2007年に実現すること(展望)
2007年に実現すること(展望)
多くの企業が各業務の可視化とその改善を行い、ツールベンダは情報技術での支援機能を供給し、情報部門はそれを活用する、という流れを受け、2007年にはBPMの本格活用がはじまります。
ビジネスの変化に迅速な対応できる情報システム環境整備の実行が見えてきた今、それぞれの対場で2007年の展望を語ってもらいましょう。
B社経営者「効率化と改善サイクルの定着が目標」
- B社経営者(取締役): 昨年から差し迫った懸案事項としてあげられる日本版SOX法と内部統制への対応が求められる。BPMの採用を決定し、小規模ながら進めてきた状況の中での 評価として、これからは自社の成熟度に合わせた身の丈の取り組みからはじめ、一過性に終わらせない体制作りが必要だと感じている。
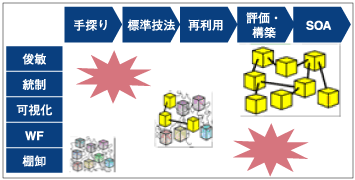
図2:企業の成熟度とBPM適用
(出典:丸山則夫プレゼン資料)
- B社経営者(取締役): BPMの当面のターゲットは内部統制となるが、真の目的は企業体質強化にある。効率化を維持しつつ、更なる継続改善サイクルを定着する仕組みを構築する。方針(展望)としては以下のものがあげられる。
- ビジネスプロセス可視化とKPIの連動の実現
- ビジネスプロセス改善に着目した新たな職能の設定
- IS部門を含めた俊敏経営のための組織作り
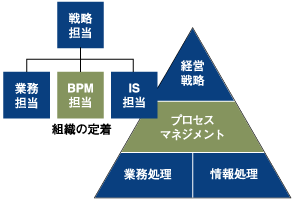
図3:定着が求められる組織作り
(出典:丸山則夫プレゼン資料)
- B社経営者(取締役): BPMSについては検討段階だが、今年中にパイロット導入を行うとともに社内スキルをシフトし、ロードマップ(導入方針)を明確にする。当然、IS部門のあり方についても見直しが必要となる。
B社実務者「担当者の配置と組織の定着をはかる」
-
B社業務担当者: 昨年後半から、内部統制の可視化を行ってきた。10年ほど前にも、BPRで全社的な業務フローをExcelで整理したことがあるが、その作業は一過性に終わってしまい財産として活かしてはいない。
今回は情報化と連動したBPMN(または製品が用意したビジネスプロセスの表記法)を採用し、業務改善を実現する仕組みの定着を前提に整理する。すでに、 ビジネスプロセス分析担当が設置され、ビジネスプロセス分析・整備の統制を試行錯誤しながらトライしている。この経験を踏まえ組織の定着をはかる予定だ。
- 管理のためだけのデータ入力をなくす
- 業務プロセス可視化・共有で情報システムのブラックボックス化を防ぐ
- 事業プロセスの透明性を恒常的に確保
- 自身のポジションを認識し実務者による改善がはかれる(経営方針を受け実施結果が担当として認識できること)
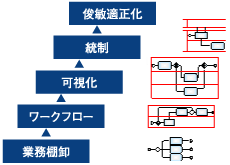
図4:ビジネスプロセスの可視化
(出典:丸山則夫プレゼン資料)
B社情報システム構築実務者「旧環境の更改をテーマに関連部署を設置」
-
B社情報システム構築実務者: 日本版SOX法や内部統制が追い風となり、情報システムの環境を変える計画を作成した。
現在の環境は10年来、そのコンセプトの変更を行っていないので旧環境の更改がテーマである。
まずはSOAの概念を採用して柔軟かつ拡張性ある基盤作りを行い、その上に日本版SOX法や内部統制を設置する。

図5:SOAの概念
-
B社情報システム構築実務者: 課題としては、COBOLベースの技術者が多数いることや、パートナーとなるベンダーがBPMやSOAを理解していないことだ。パートナー企業の見直しや IS部門のスキルの再設定、技術者の育成をはかっていく。SOAの採用は容易だとは考えておらず、基盤として定着するまでには数年かかるだろう。しかし、 その概念についての理解と実践的な構築法は今年中に定着させたい。
BPMの活用の面では、ビジネスプロセスの分析担当部門を設置し、その結果を踏まえてシステム構築の要件をまとめられる人材を確保することを方針とする。


















